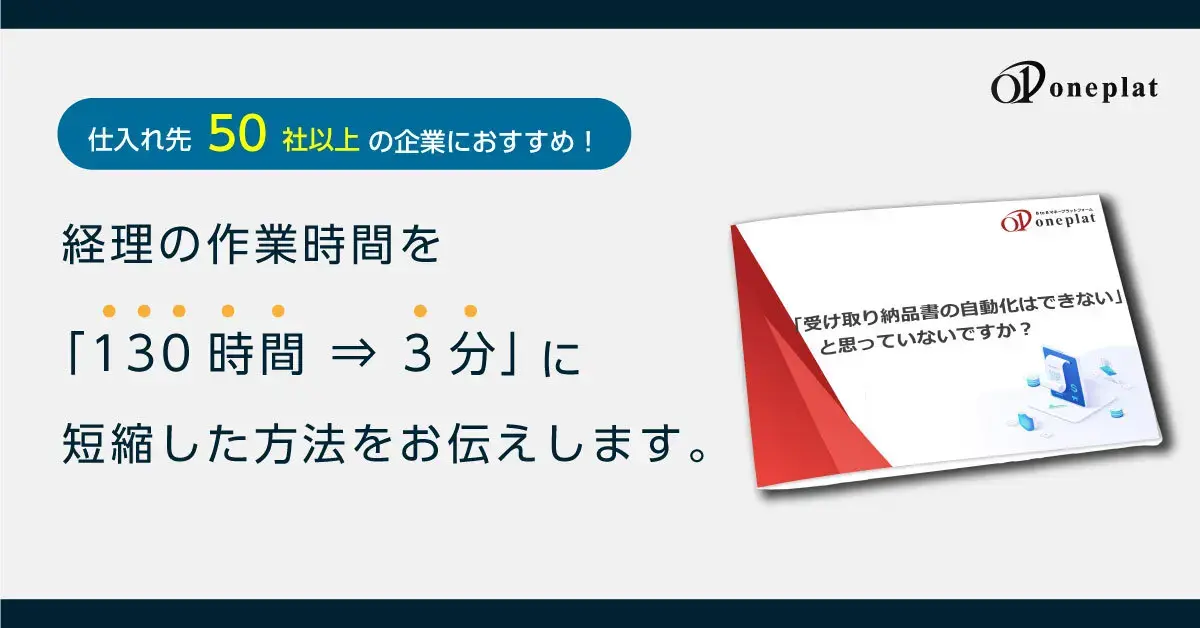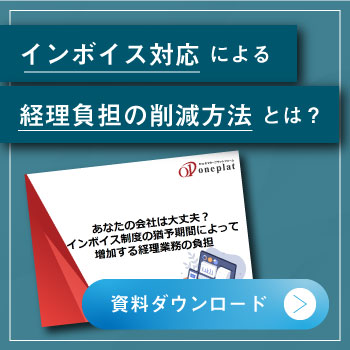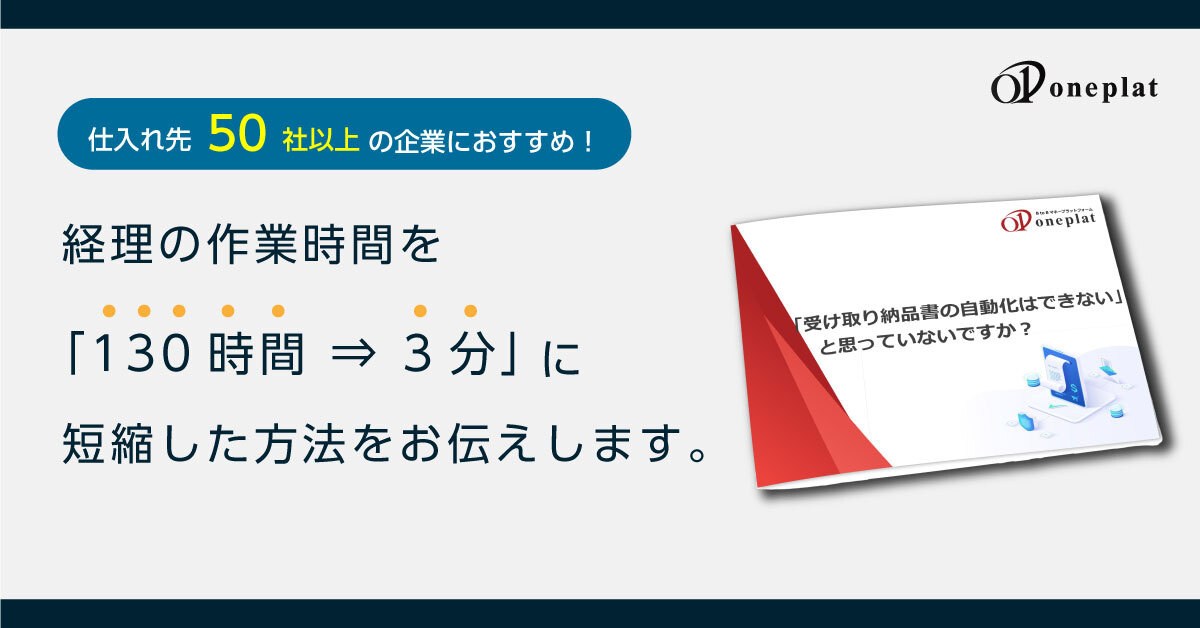脱ハンコのニュースはよく見るけど「結局いつからなんだろう?」「会社にはどのタイミングで導入しよう」と考える担当者の方は多いのではないでしょうか。本記事では、脱ハンコの現状を解説をしています。脱ハンコのタイミングや、脱ハンコが不可能な書類についても紹介するため、是非脱ハンコ導入のご参考にしてみてください。
脱ハンコはいつから?

脱ハンコという言葉を最近よく聞くという方は多いと思います。
ニュースでも、行政手続きの押印の99.4%が廃止されると発表があり、定期的に話題となる脱ハンコですが「実際いつから脱ハンコが行われるのか」という、脱ハンコの詳細を理解している方はまだまだ少ないです。
この章では脱ハンコの現状について詳しく解説していきます。
行政手続きの押印廃止
まずはじめに、行政手続きの押印廃止は一体いつから開始されるのかを見ていきます。
これまでは、税務署に提出する確定申告書等の税務関係書類は、国税に関する法令に基づいて、提出者の押印をしなければならないとされていました。
しかし、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降は税務関係書類の押印廃止が本格的に始まり、一定の書類を除き押印を必要としないこととなりました。つまり、既に行政手続きの脱ハンコは始まっていると言えます。
脱ハンコの現状
では、次に脱ハンコがどのくらい進んでいるかを見ていきます。
内閣府が令和3年4月に公表した資料によると、令和3年3月末時点で押印を求める行政手続きの全数15,611手続きのうち、15,493手続き(97.4%)が押印廃止の決定、または廃止の方向で検討されています。
このように行政の多くは、既に脱ハンコが行われています。
出典:内閣府|書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について
企業の脱ハンコの動き
では、企業の脱ハンコの動きはどうなのでしょうか。
行政における脱ハンコの流れは、民間企業の取引においても多大な影響を与えています。
さらに社会のデジタル化の流れや、コロナによるリモートワークという働き方が相乗効果を生み、多くの企業が脱ハンコを検討し、電子印鑑への転換を目指しています。
既に日本を代表する大企業をはじめとして、業界を問わず脱ハンコの動きが活発化しており、既に脱ハンコを取り入れている企業ではその成果を実感していると言います。
日本のハンコ文化

ここからはハンコ文化の現状と必要性について解説します。
日本がスムーズに脱ハンコに移行できない理由には、国内に深く根付いたハンコ文化が関連しています。
ハンコ文化の現状
日本に深く根付いているハンコ文化。必要性が低い企業でも脱ハンコができていない理由がこのハンコ文化そのものです。
前述したように、コロナ禍においてリモートワークが増えましたが、押印をするためだけに出勤しなければならない「ハンコ出社」があると問題になっていました。
脱ハンコを行うことでそういった手間は省けます。しかし、日本特有の組織改革のしにくさや、深く根付いた慣習を変えなければならないという文化的要因が、脱ハンコの推進を阻んでいます。
ハンコの必要性
では、そもそもハンコはなぜ必要なのでしょうか。
まず契約を行う際は、証拠を残すために文書にします。その上で、偽造等の問題を防ぐために、証拠保全を行うために相手方からハンコがある書面をもらうのです。
契約をするときは良好でも、その後関係が悪くなることがあります。そういった時のために契約書を作成し合意した内容を記録しておいたり、経理上でも別の会社からお金が振り込まれた際に、それが借りたものか、売上なのか、契約書を見てすぐわかるようにしておきます。
このように、事実を客観的に確認できるように残すために契約書を作成し、ハンコをもらうことで保険を作っておくためのものです。
しかし、今の時代それをアナログで行うのは効率が悪いですし、近年厳しくなってきたセキュリティ的な問題も発生します。
それなら、脱ハンコができそうなものはしてしまった方が効率が良いですよね。
次の章では、すぐに脱ハンコができそうなものをご紹介します。
すぐに脱ハンコができそうなもの

ここでは、すぐに脱ハンコができそうなものをご紹介していきます。
・受領印
・議事録等
・請求書・見積書
・発注書・注文書
・領収書
脱ハンコの代わりになるものはサインです。
上記の5つは、前述したような慣習的に押印を行っているものなので、基本的にサインで代用しても問題のないことが多いです。
しかし、請求書・見積書や発注書・注文書に関しては、取引先に押印してくれと言われた場合は対応した方が良いでしょう。
脱ハンコがしにくいもの

ここまでは、押印がなくても大丈夫なものをご紹介しましたが、ここからは押印したほうが良いものをご紹介します。
・割印
・雇用契約書等の契約書類
・署名されていない書類
・割印
割り印は契約書の偽造を防止するために押されています。
これを無くしてしまうと、複数ページある契約書の途中をすり替えられてしまい不利益を被る可能性があります。
・雇用契約書等の契約書類
雇用契約書や業務委託契約書等の契約書類はトラブルが発生した際、訴訟へ発展することがあります。
その際に、印鑑を押していないとその契約が有効であると、判断してもらえないためこれも押印しておきましょう。
・署名されていない書類
「署名捺印」と「記名押印」の違いはご存知でしょうか。
署名捺印は、自筆で書いた名前と押印
記名押印は、自筆以外の記名、(印刷含む)名前と押印
と分けられています。
上記のうち裁判となった際に、署名捺印は押印がなくとも法的な効力が発生しますが、記名押印は押印がなければ記名のみの書類となってしまうため、法的な効力を果たさないので注意が必要です。
また、押印ではなく電子印鑑が認められている書類も多くあります。
次の章では、押印の代わりになる電子印鑑をご紹介します。
注目される「電子印鑑」

電子印鑑とは、PDFファイル等の電子文書へ捺印できる印鑑データのことをいいます。紙文書への捺印とは異なり、オンライン上でも契約書を確認して捺印することができるため、リモートワークでも契約が結べます。
法的効力が求められる書類も、この電子印鑑を利用することで脱ハンコを行うことができ、業務を効率化させることができます。
【関連記事】請求書への押印は電子印鑑で対応可能?有効性や作り方を解説
納品書・請求書の脱ハンコなら電子化がおすすめ
ハンコを使用する機会が多い納品書や請求書を電子化することで、脱ハンコだけでなく業務効率化やセキュリティ強化も実現します。以下に、主なメリットを解説します。
押印作業をなくせる
紙ベースの業務では、押印作業のためだけに出社しなければならない「ハンコ出社」が長年の課題でした。
納品書や請求書を電子化することで、どこにいてもオンラインで確認・承認できるようになります。出張中でも対応可能な上、テレワークの推進にもつながります。
印鑑の不正使用を防ぐ
紙の請求書では、担当者が不在の際に「少し借りて押しておこう」と軽い気持ちで印鑑を使用するリスクがあります。しかし、こうした行為は印章偽造罪にあたり、企業全体の信頼性を損ねる原因になります。
一方、納品データや請求データであれば電子印鑑が利用可能です。さらに電子証明書やタイムスタンプも付与することで印鑑の不正使用を回避できるでしょう。
取引先とのやり取りがスムーズ
納品書や請求書をデータに切り替えれば、メールやクラウドを活用して迅速なやり取りが可能になります。「押印が間に合わない」「書類が郵送できない」といった従来のトラブルを簡単に解消できるのは大きなメリットでしょう。
例えば、支払期限が差し迫った請求書であっても、すぐに送付して確認を取れます。その結果、取引先との信頼関係がさらに深まり、ビジネス全体の効率向上につながります。
脱ハンコ・業務効率化を目指すなら「oneplat」
「脱ハンコを進めたいけれど、具体的にどう進めればいいのかわからない」と悩んでいるご担当者様も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが、納品書・請求書の電子化サービス「oneplat(ワンプラット)」です。
oneplatは、低コストで導入できるうえ、充実したサポートを無料で提供しており、導入いただいた多くの企業様から高い評価を得ています。以下に、oneplatの主な特徴をご紹介します。
月額33,000円で手軽に導入
電子化を検討する際に気になるのがコストですが、oneplatは初期費用がかからず、月額33,000円(税込)で利用可能です。
月額固定制のため、書類の枚数や取引先の数に関係なく同じ料金で利用できるのが魅力です。また、サポート料金も無料なので、安心して導入を進められます。
請求書の承認・入金が効率化
oneplatでは、2次承認・3次承認といった段階認証に対応しており、承認権限を柔軟に設定できます。さらに、納品書や請求書はクラウド上で管理されるため、パソコンだけでなくスマホからもアクセス可能です。
また、納品・請求データは総合振込データに変換され、ネットバンキングへの送信や振込手数料の自動計算も可能なため、業務のスピードアップが期待できます。
取引先様への案内も無料
「取引先に電子化をお願いするのが難しいのでは?」と心配される方もいるでしょう。
oneplatでは、取引先へのサービス案内を無料で代行します。
メリットや操作方法を丁寧に説明することで、良好な関係を保ちながらスムーズに電子化を進めることが可能です。
まとめ:脱ハンコは既に始まっている!

今回は脱ハンコやハンコ文化の現状や、脱ハンコを始められる書類、そして脱ハンコしにくい書類とその解決手段をご紹介しました。
本文中でも記載したように、脱ハンコはもう既に始まっています。しかし、日本に深く根付いているハンコ文化から抜けきれていない企業もまだたくさんあります。
しかし、脱ハンコはデジタル化が進む社会で生き残るために避けては通れない道です。
今すぐに、すべてを脱ハンコさせるのは大変ですが、身近なところから少しずつ脱ハンコを進めてみましょう。