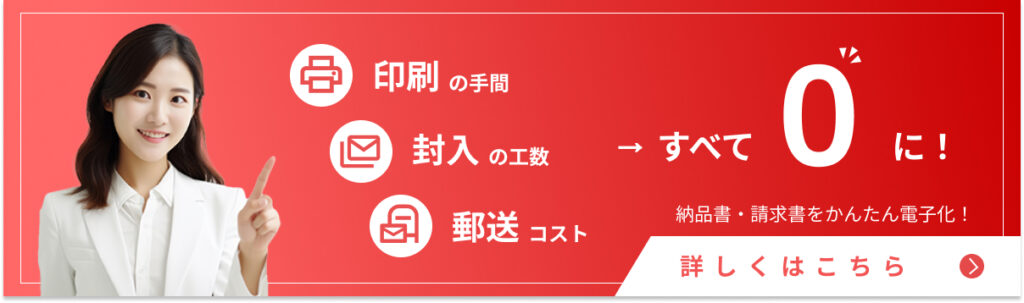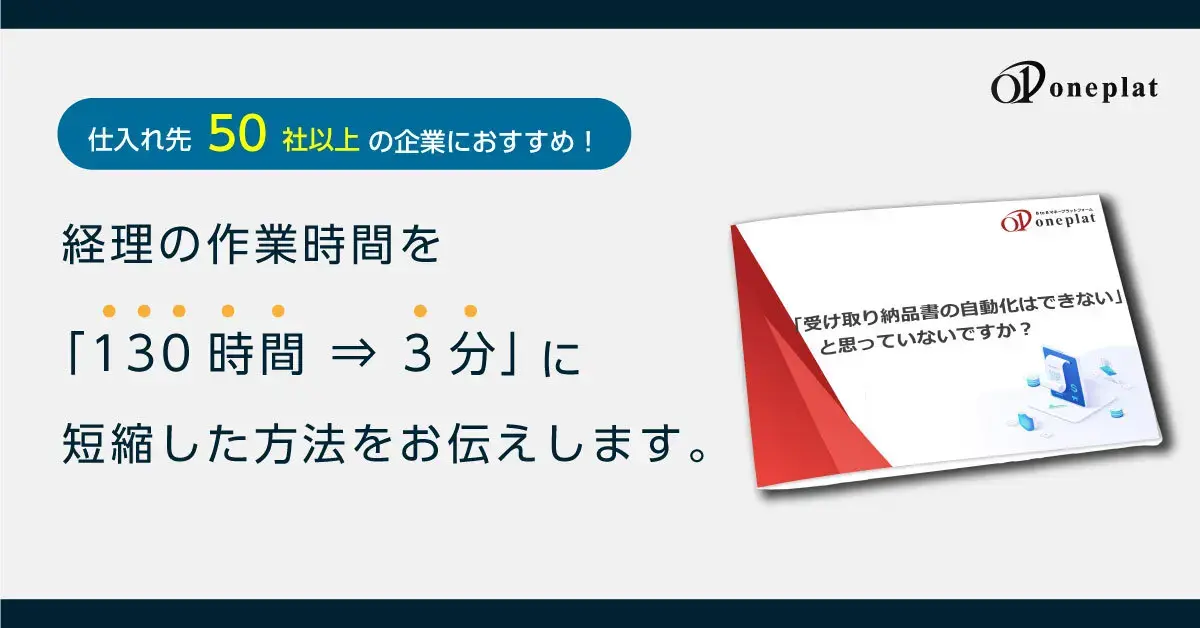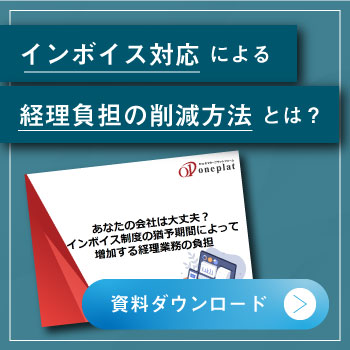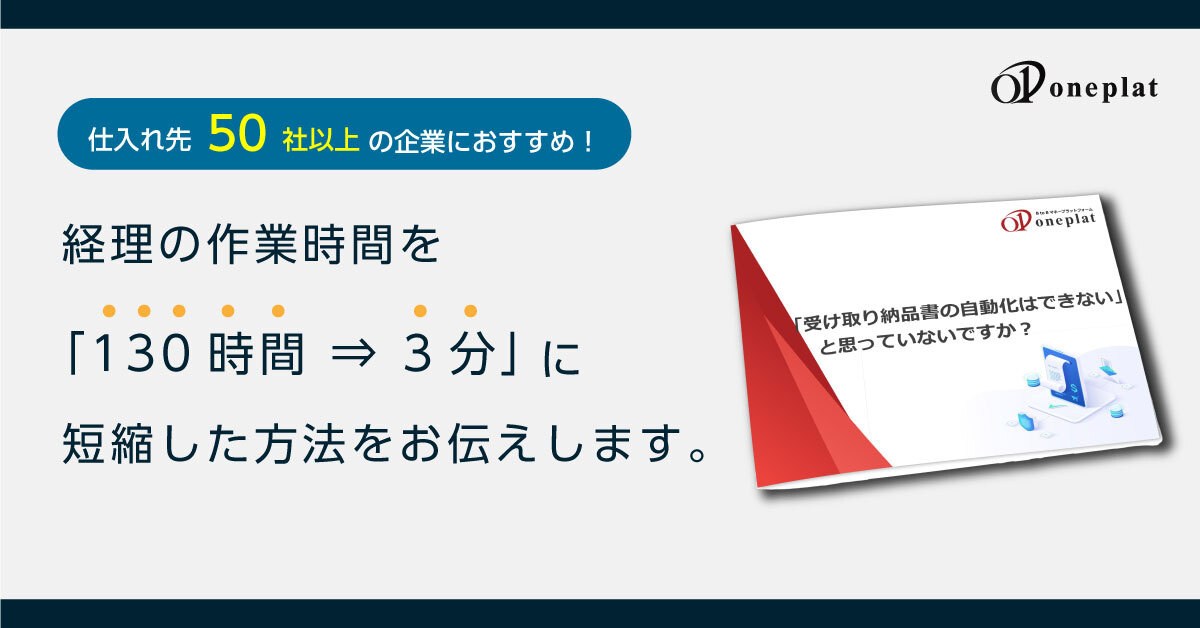紙の請求書や納品書は手作業での処理が多いため、金額や日付の書き換え、架空請求、押印の偽造などの不正が発生しやすいという課題があります。
もし、自社の名義で不正な請求書が発行されてしまえば、金銭的な損失や信用の失墜につながるかもしれません。
本記事では、請求書の改ざん・偽造によるリスクや、発覚した際の適切な対応方法について詳しく解説します。また、不正を防ぐための具体的な対策や、電子化でリスクを最小限にするメリットについてもご紹介します。
発行する納品書・請求書の改ざんや偽造とは?
納品書・請求書の改ざんや偽造とは、本来の書類を不正に書き換えたり、架空の書類を作成したりする行為を指します。
取引先を騙して不正な利益を得る目的で行われることもあれば、社内の経理処理を偽装するために行われることもあります。
紙の書類を使用している場合、手書きの修正や印鑑の偽造が比較的簡単に行えてしまうため、特に注意が必要です。
請求書の改ざんや偽造には様々な手口がありますが、特に多く見られるケースをご紹介します。
水増し請求
水増し請求とは、本来支払う必要のない金額を請求したり、実際の取引額よりも高い金額を請求したりすることです。例えば、数量を実際よりも多く記載し、代金を受け取る行為は、詐欺罪や業務上横領罪に該当します。
架空請求
架空請求とは、実際には存在しない取引先の名義を使い、提供していないサービスや商品に対して請求書を発行する行為を指します。
特に、請求書の支払期限が異常に短い場合は、十分な確認を行わずに支払いを済ませてしまうケースがあります。
署名の偽造
上司や経理担当者の印鑑を無断で使用したり、電子署名を偽造したりして、不正な請求を通そうとする手口です。
例え「担当者が不在だったから代わりに押印した」という意図であったとしても、私文書偽造罪に該当する可能性があるため注意が必要です。
振込先の書き換え
請求書の振込口座だけを変更し、企業の資金を別の口座へ送金させます。既存の請求書を少し改ざんするだけで実行できるため、取引先が気づかずに誤って振り込んでしまうリスクが非常に高いです。
納品書・請求書の改ざんや偽造による発行側のリスク
納品書や請求書が改ざん・偽造された際、発行した企業にどのような影響が及ぶのでしょうか。
単なる書類上の問題にとどまらず、金銭的な損失や信用の低下、業務負担の増加など、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。
以下では、納品書・請求書の改ざんや偽造がもたらす主なリスクについて解説します。
損害賠償が請求される
納品書や請求書の改ざん・偽造によって被害が発生した場合は、不正を行った従業員は損害賠償の責任を負うことになります。
しかし、企業にも「使用者責任(民法第715条)」があるため、従業員が行った不法行為の責任を会社も負わなければなりません。
過去には、取引先から損害賠償請求を受け、損害額の全額を会社が負担したケースも存在します。
信用が失墜する
請求書の改ざんや偽造は、文書偽造罪・変造罪、詐欺罪、業務上横領罪などの犯罪に該当し、懲役刑が科される可能性があります。
個人の犯行であっても多くの場合、取引先や顧客は「会社が防止できなかった」と判断するため、企業の信用は大きく損なわれてしまうでしょう。長年築き上げてきた取引関係が破綻し、取引拡大のチャンスも失ってしまいます。
業務効率が低下する
納品書や請求書の改ざん・偽造が疑われた場合は、関係書類の精査や取引先との照合を行わなければならず、膨大な時間と労力が必要とされます。
特に、紙の書類で管理している場合は過去の情報を手作業で探す必要があり、問題の特定に時間がかかるでしょう。
さらに、社内の管理体制を見直し、再発防止策も検討しなければいけません。その結果、本来の業務が滞り、企業全体の生産性が大きく低下してしまいます。
発行した納品書・請求書の改ざんや偽造に気付いた場合の対応
万が一、発行した納品書や請求書の改ざん・偽造が発覚した場合は、迅速に対応することが不可欠です。対応が遅れると、被害の拡大につながり、取引先や関係者との信頼関係が大きく損なわれるリスクがあります。
ここでは、改ざんや偽造に気付いた場合の対応についてご説明します。
社内での初動対応
まずは、どの書類が対象なのか、どの部分が改ざんされたのか、誰が関与したのかを徹底的に調査します。発行履歴や過去の記録と照合し、不正が発生した時点を特定しましょう。
あわせて、経理部・総務部・法務部などの関係部署と連携し、対応方針を決定します。
取引先への対応
改ざんや偽造が取引先に関わる問題であれば、誤解や信用の低下を防ぐために、迅速かつ誠実に対応することが重要です。
誤った請求書を送付してしまった場合は、すぐに取引先へ事情を説明した上で、正しい書類を再発行しましょう。既に誤った金額で支払いが行われている場合は返金手続きを速やかに進めます。
また、口頭での説明だけでなく、書面やメールで正式に報告し、企業としての誠意を示すようにします。
再発防止の策定
内部調査を徹底し、問題の根本原因を特定した上で、効果的な再発防止策を講じることが重要です。詳しくは次項にて解説しています。
納品書・請求書の改ざんや偽造を防止するための対策
改ざん・偽造を防ぐには、多方面からの対策を講じる必要があります。ここでは、納品書や請求書の不正を防ぐために有効な具体策を紹介します。
発行・承認フローの見直し
納品書や請求書の作成から承認、発行に至るまでのプロセスを厳格に管理することで、不正が入り込む余地を減らすことができます。特に、金額・取引内容・振込先のチェックを複数の担当者で行う仕組みを整えるとよいでしょう。
大きなコストをかけずに実施できますが、確認作業を追加することで業務負担が増大するという点はデメリットです。
【関連記事】課題が多い請求書発行・支払いのチェック作業。業務フローに沿って効率化するための方法をご紹介
セキュリティ対策を強化する
請求書の改ざんや偽造を防ぐには、書類の改変を困難にする仕組みを導入することが効果的です。
例えば、鍵付きのキャビネットに常時保管する、納品書や請求書の発行日時や担当者などを記録し後から追跡できるようにする、といった方法が挙げられます。
納品書・請求書電子化サービスを導入する
納品書・請求書の電子化サービスを導入する方法です。タイムスタンプの付与やアクセス権限の管理、修正履歴の記録などの機能が利用できるため、紙の納品書・請求書よりも改ざんや偽造のリスクを低減することが可能です。
また、電子化サービスの導入は納品書・請求書発行時の不正を防止できるだけでなく、紙書類と比較して業務効率化やコスト削減にも期待できます。
ただし、電子帳簿保存法によって「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件が定められています。法令遵守と不正防止の両方を実現するには、電子帳簿保存法に対応した請求書電子化サービスを導入するとよいでしょう。
【関連記事】請求書を電子発行するメリットは大きい!効率的な運用方法と電子発行時の注意点
電子化で請求書改ざん・偽造のリスクを最小限に
紙の請求書は、手作業での記入や押印が多いため、金額や日付を書き換えられるリスクが常に伴います。しかし、請求書や納品書をデータに切り替えることで、改ざんや偽造を効率的に防ぐことが可能です。
以下に、請求書や納品書を電子化した際の具体的なメリットをご紹介します。
作成・修正の記録が残る
電子化によってタイムスタンプを付与することができます。タイムスタンプとは、ある時点にその電子データが存在していたこと、それ以降改ざんが行われていないことを証明する技術のことです。発行日時が明確になるだけでなく、後から書き換えられた場合でも修正履歴が残るため、不正の抑止力としても有効です。
2022年に改正された電子帳簿保存法では、タイムスタンプに関する要件が一部緩和されました。
【関連記事】電子化した請求書と納品書の保存期間は?電子帳簿保存法の概要
電子署名を付与できる
電子署名は、「電子文書が署名者本人によって作成されたこと」および「署名後に改ざんされていないこと」を証明します。
これにより、発行者の正当性を保証するとともに、不正な書き換えが行われた場合でも検出できるため、安全性が飛躍的に向上します。
業務効率化・コスト削減にもつながる
紙の請求書は印刷・封入・郵送などの手間がかかりますが、電子化することでこれらの作業を削減することができます。また、書類は切手代や印刷代が発生しますが、電子化すればコストを抑えることが可能です。
発行する納品書・請求書の改ざんや偽造を防止するなら「oneplat(ワンプラット)」
納品書や請求書の改ざん・偽造を防ぐには、電子化サービスの導入が効果的です。
しかし、「導入に時間がかかりそう」「コストが高いのでは」と不安を感じる企業も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、低コストで導入でき、スピーディーに電子請求書の運用を開始できる「oneplat(ワンプラット)」です。
システム連携で一括発行
oneplatは、CSV連携が可能な様々な販売管理システムや会計システムとの連携が可能です。
例えば、現在ご利用中のシステムからCSVデータを取り出し、oneplatに連携するだけで、取引先への納品書・請求書をワンクリックで一括発行することもできます。
手作業での入力が不要になるため、水増し請求や振込先口座の書き換えなどの不正リスクを大幅に低減できます。
受け取り状況を確認可能
oneplatで発行した請求書は即座に販売先へ送信され、受け取り状況をシステム上でリアルタイムに確認可能です。また、未開封の請求書がある販売先には、自動でリマインドメールを送信する機能も搭載しています。
これにより、請求書の受け取り漏れや不正な請求書の送付を防ぐことができます。
低コスト&スピーディーに電子化を実現
oneplatの料金プランはシンプルで、初期投資は0円、月額22,000円(税込)でご利用可能です。納品書の発行も併せて行う場合は、月額33,000円(税込)です。
さらに、導入時の初期設定もサポートに含まれています。担当者の負担を減らしつつ、電子化に移行することができるでしょう。
まとめ
紙ベースの請求書は偽造が容易で、さらに管理の手間やコストがかかるという課題があります。
しかし、請求書や納品書を電子化することで、セキュリティを強化しながら業務の効率化を図ることができます。
特にoneplatなら、費用を抑えながら短期間で電子化が可能です。安全かつスムーズな請求業務を実現するために、是非oneplatの導入をご検討ください。