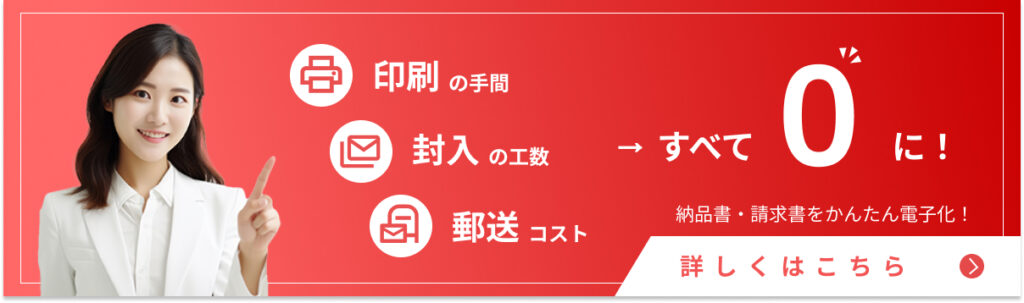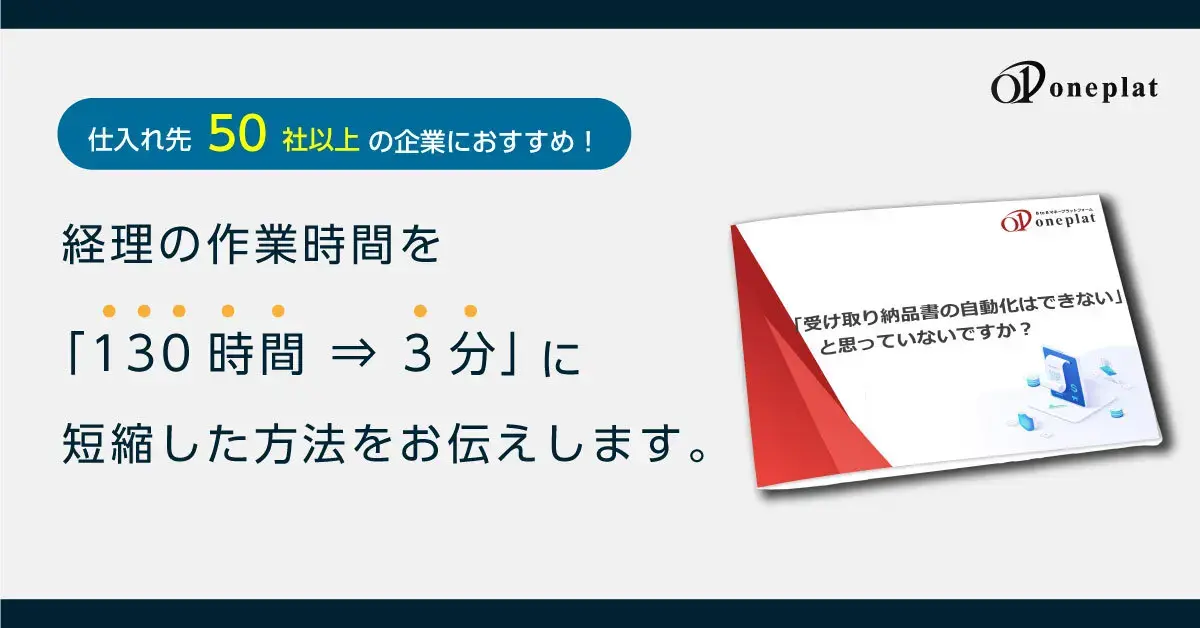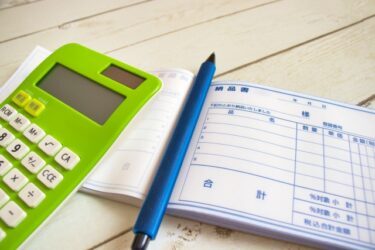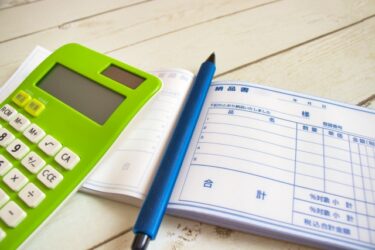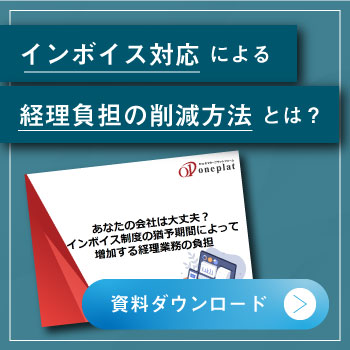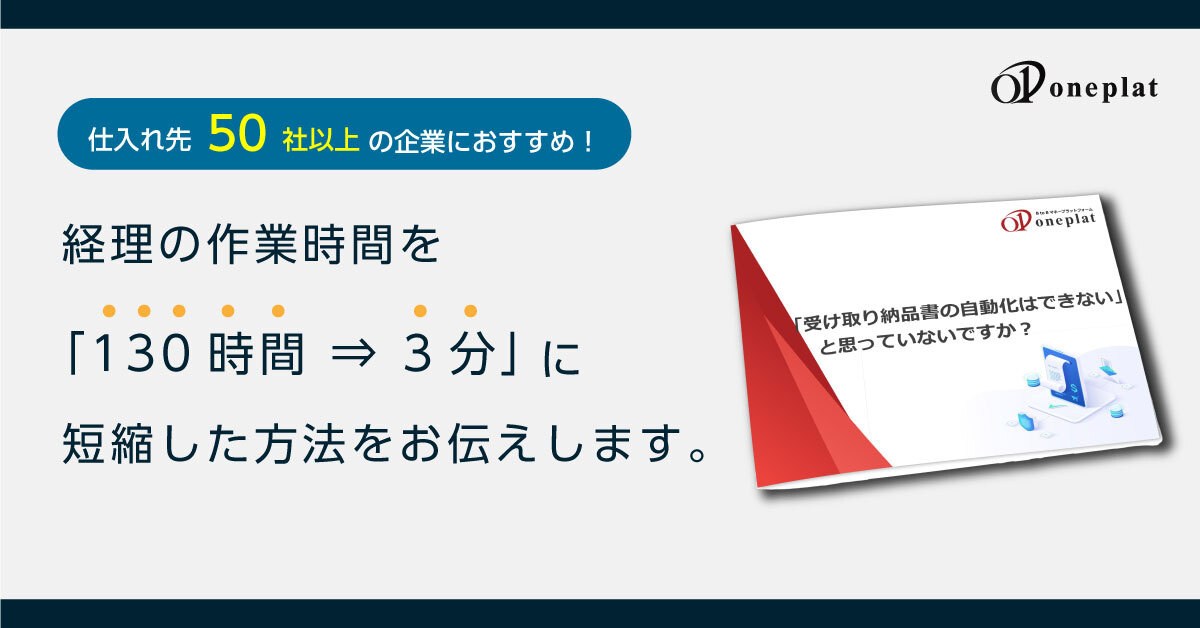納品書を送付する際に「納品書在中」を記載することは、取引先の担当者にスムーズに届きやすくなったり、重要書類として認識してもらえるようになったりする等、多くのメリットがあります。
しかし、納品書を送付するたびに手書きするのは意外と手間がかかるため、「スタンプで済ませても問題ないか」「そもそも、記載は必須なのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
そこで本記事では、「納品書在中」の記載ルールや、納品書送付時のマナーについて解説します。さらに、紙の納品書にかかる手間やコストを削減する方法についても紹介しますので、是非最後までご覧ください。
「納品書在中」を記載する理由
封筒に「納品書在中」と記載することは、法律で義務づけられているわけではありません。
しかし、記載することで得られるメリットは多く、実務上多くの企業で記載されています。
主な理由として、以下の3つが挙げられます。
担当者にスムーズに届けられる
企業には毎日、大量の郵便物が届きます。特に、大企業や事務所の受付では、封筒の中身を1つずつ開封・確認するのが遅れ、担当者に届くまで時間がかかる場合もあります。
「納品書在中」と明記されていれば、封筒を受け取った従業員がすぐに中身を把握できるため、納品書を必要とする担当者へスムーズに届けられます。
重要書類として認識してもらえる
何も書かれていない封筒は、DM(ダイレクトメール)やその他の一般郵便と混ざってしまい、後回しにされる可能性があります。
「納品書在中」と記載することで、封筒を確認する人が「重要な書類」と認識し、優先的に担当者へ渡してくれる可能性が高まります。これにより、確認漏れや処理の遅延を防ぐことができます。
取引先からの信頼度が高まる
「納品書在中」と明記することで、受け取った企業側は封筒を開封し、中身を確認・分類する手間が減ります。
こうした配慮が、「マナーを理解している」「細かいところまで心遣いができる」という良い印象につながります。
納品書在中の記載箇所と書き方
「納品書在中」の記載に厳密な決まりはありませんが、一般的に採用されているルールがあります。
縦書きなら左下、横書きなら右下に記載
縦書きの封筒では宛名の左下、横書きの封筒では宛名の右下に記載するのが一般的です。
この位置に記載すれば、手に取った際すぐに内容を把握できます。ただし、封筒の中身が納品書であると一目で分かることが重要であるため、必ずしもこの位置に記載する必要はありません。
文字色は青が無難
「納品書在中」の文字色にも決まりはありませんが、黒色だと宛名と同化して目立ちにくくなるため、別の色を選ぶのが望ましいです。
青色は視認性が高く、相手に適切な印象を与えやすいため、広く使用されています。
赤色のほうが目立ちやすいと思うかもしれませんが、「赤字」を連想させるため、ビジネスシーンでは避けたほうがよいでしょう。
定規で四角く囲む
手書きで「納品書在中」と記載する場合は、文字を四角く囲むとより目立ちやすくなります。フリーハンドでは形が崩れやすいため、定規を使ってきれいな直線で囲みましょう。見た目が整い、相手に丁寧な印象を与えることができます。
「納品書在中」以外に書く言葉
納品書と一緒に請求書や領収書を同封する場合は、「納品書・請求書在中」「納品書・領収書在中」のように記載しても構いません。
また、個人情報や機密情報が含まれている場合は、宛名本人以外が開封しないよう「親展」を付け加えるのもよいでしょう。
スタンプやハンコも可能
毎回手書きするのが面倒に感じる場合は、スタンプやハンコを活用すると効率的です。
手書きと違って書き損じの心配がなく、字体が統一されるため、見た目も整いやすくなります。
ただし、インクがかすれて一部が写らなかったり、にじんで文字が読みにくくなったりすることがあるため、押した後は必ず確認しましょう。
納品書送付のマナーと注意点
納品書を送付する際はマナーを守ることが重要です。特に注意したいポイントをまとめたので、チェックしてみてください。
封筒のサイズ
ビジネスシーンでは、A4サイズの書類を使用するケースがほとんどです。
長形3号(120mm×235mm)の封筒を使用すれば、送付状と納品書を三つ折りにすることでちょうど収まり、定形郵便として発送できます。
書類を折らずにそのまま送りたい場合は、クリアファイルに挟んでから角形2号(240mm×332mm)の封筒に入れましょう。
書類の向き
封筒を開けた際に、すぐに内容が確認できる向きで封入するのが基本です。封筒を裏向きにし、納品書の上部分が右側にくるように入れましょう。
送付状を同封する場合は、納品書の前に重ねます。
宛名
宛名に誤りがあると書類がスムーズに届かない原因となるため、正確に記入しましょう。
- 担当者名がわかる場合:「会社名+部署名+役職+担当者名+様」
- 担当者が不明な場合:「会社名+御中」
また、会社名を記載する際に、(株)や(有)と省略するのはマナー違反です。「株式会社」「有限会社」と正式名称で書きましょう。
送付状
ビジネスシーンでは、書類を送付する際は送付状(送り状/添え状)を同封することがマナーとされています。
送付状に記載すべき内容は、送付年月日、宛名、差出人、挨拶、同封書類の内容と部数です。
【関連記事】【送付状ってどう書くの?】添付する種類別に送付状の作成の仕方を解説
切手
封筒のサイズや書類の厚み、書類の枚数によって郵便料金は変動します。料金が不足している場合は返送されるか、受取側で不足分を支払うことになります。
必要な切手を確認し、適切な種類を貼るようにしましょう。
【関連記事】【2024年10月実施】郵便料金の値上げ内容を解説|納品書・請求書郵送への影響とコスト削減方法をご紹介
同封物
商品を発送する際に納品書を同梱するケースもありますが、注意が必要です。
納品書は封を閉じた状態で送ると「信書扱い」となり、宅配便での送付が法律で禁止されています。
ただし、封をせずに納品書を同梱する場合は「添え物」として扱われ、宅配便での送付が可能です。
紙の納品書ならではの課題
以下では、納品書を紙ベースで運用する際の課題について解説します。
時間と手間がかかる
紙の納品書を作成する際、データの入力や取引先ごとのフォーマット調整等、多くの工数が発生します。
また、これまで解説してきた「納品書在中」のルールやマナーも考慮しながら作成・送付しなければならず、正しく対応するだけでも大きな手間がかかります。
ヒューマンエラーが発生しやすい
手作業が多いほど、入力ミスや送付ミスが発生するリスクが高まります。例えば、納品書を封筒に入れる向きを間違えたといった些細なミスでも、取引先に不信感を与える原因になりかねません。
さらに、金額や数量を誤って記載した納品書を送付してしまうと、再発行や再送手続き、謝罪対応が必要になり、余計な業務負担が発生します。
コストが増大する
紙の納品書を発行するには、印刷用紙、インク、封筒、切手といったコストがかかります。
1回あたりの費用は少額でも、年間で見れば相当なコストになっているでしょう。
納品書を電子化するメリット・デメリット
紙の納品書は作成から送付までの手間が多く、コストもかかるのが課題です。そのため、業務の効率化を進めるなら、電子納品書への移行が有力な選択肢となります。
ただし、すべての取引先が納品書の電子化に対応しているとは限らないため、慎重に検討したほうがよいでしょう。
以下に、納品書を電子化するメリット・デメリットをまとめましたので、ご参考ください。
納品書を電子化するメリット
- システム上で作成・送付できるため、印刷・封入・郵送が不要になる
- 取引先ごとにテンプレートを設定すれば、短時間で発行可能
- 用紙、インク、封筒、郵送費が不要になり、経費を大幅に削減できる
- 宛名や金額等を自動入力できれば、記入ミスや送付ミスを防ぎやすい
- 送付履歴が残るため、「送ったはずの納品書が届いていない」といったトラブルも回避可能
- メールやクラウドで送付できるため、取引先がすぐに確認可能
- 紙の納品書よりも紛失・破損するリスクが少ない
- 電子帳簿保存法やインボイス制度等、最新の法律に対応しているサービスが多い
納品書を電子化するデメリット
- 紙の納品書を希望する取引先もあるため、事前の確認が必要
- 紙と電子を併用する場合は、管理が煩雑になる場合がある
- 電子化サービスによっては、高額な初期導入費用や月額利用料が発生する
- 担当者への教育や社内ルールの整備が必要
なお、デメリットは納品書・請求書の電子発行サービスによって解消できる場合があります。以下の記事では、電子納品書の導入を検討する際に重要なポイントを解説していますので、ご参考ください。
【関連記事】【紙ベース/アナログ管理企業向け】納品書・請求書電子発行サービスの選び方を基礎から解説
納品書の発行・送付を効率化するなら「oneplat(ワンプラット)」
納品書の発行や送付にかかる手間を減らしたいなら、電子化が有効な解決策です。
「oneplat(ワンプラット)」は、納品書や請求書の発行・送付・管理を一元化できるクラウドサービスで、多くの企業で採用されています。
oneplatを導入すれば、納品書のペーパーレス化が可能に。「納品書在中」の記載を作成する必要もなく、送付状の細かなマナーを気にする手間もなくなります。
例えば、現在利用中のシステムからCSVデータを取り出し、oneplatに連携するだけで、取引先全社への納品書・請求書の発行がワンクリックで完了します。
直感的な操作で利用できるため、実務担当者はもちろん、販売先の企業側もスムーズに活用可能です。
さらに、導入コストも抑えられるのも魅力です。請求書の電子発行は月額料金22,000円、納品書と請求書を電子発行する場合でも月額料金33,000円(税込)のみでご利用いただける上、初期費用やサポート費用はかかりません。
まとめ
納品書の発行・送付には、細かなルールやマナーがあり、紙ベースでは手間もコストもかかるのが現状です。
しかし納品書を電子化することで、「納品書在中」や宛名の記載、送付状の作成等の作業が不要になり、業務の負担が大幅に削減されます。
oneplatは請求書の発行・送付もワンクリックで完了するため、作業の効率が飛躍的に向上します。シンプルな操作で利用できるため、電子化が初めての企業や、これまで紙ベースの書類管理がメインの企業でも迅速、かつスムーズに導入可能です。
納品書・請求書に関する業務を改善したい方は、是非一度oneplatにご相談下さい。