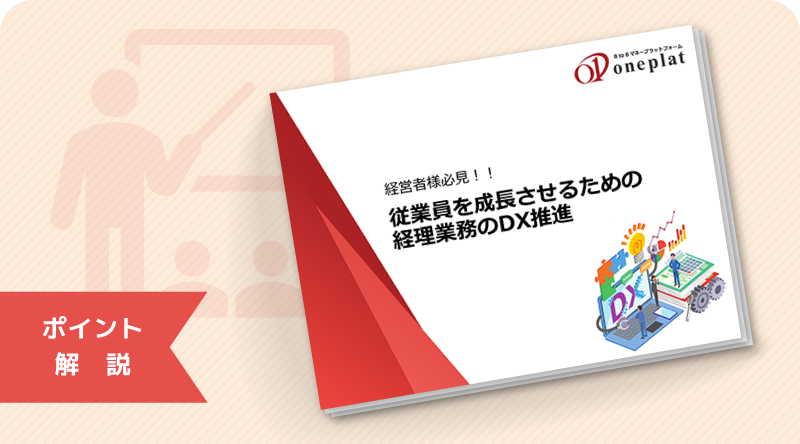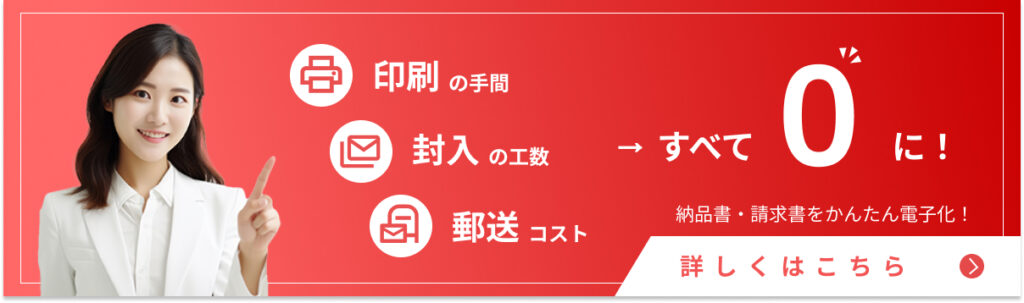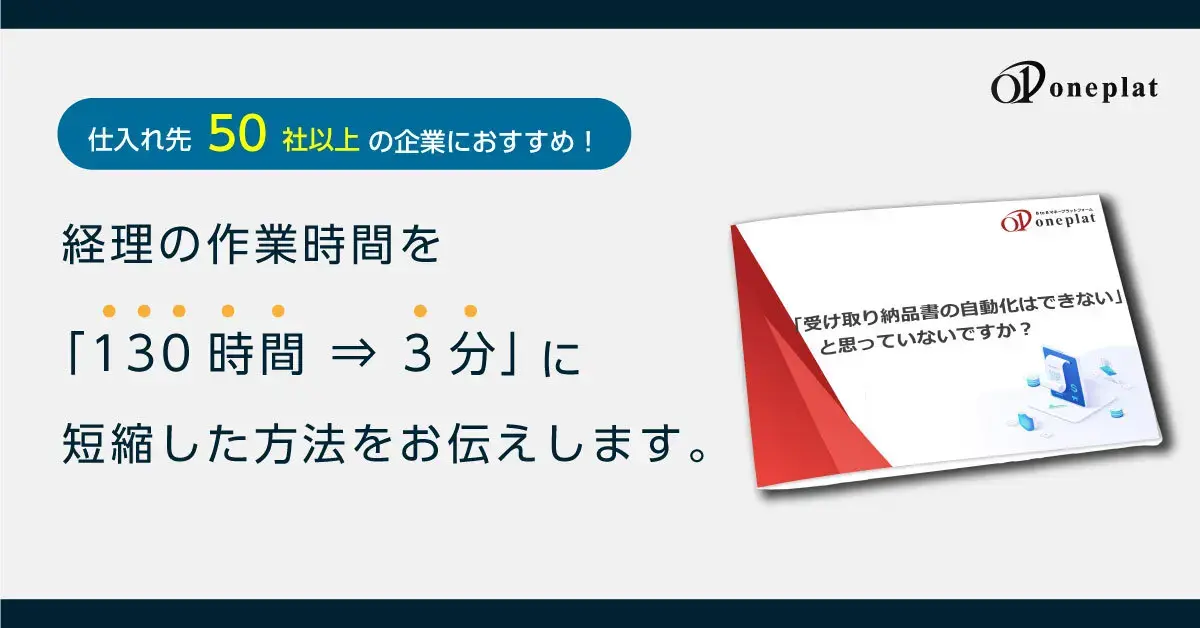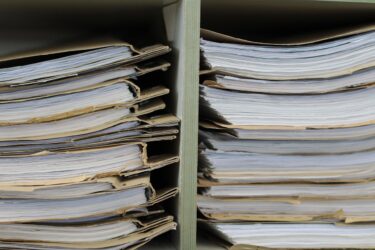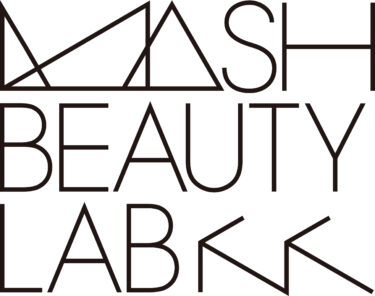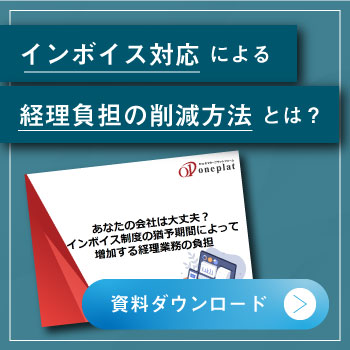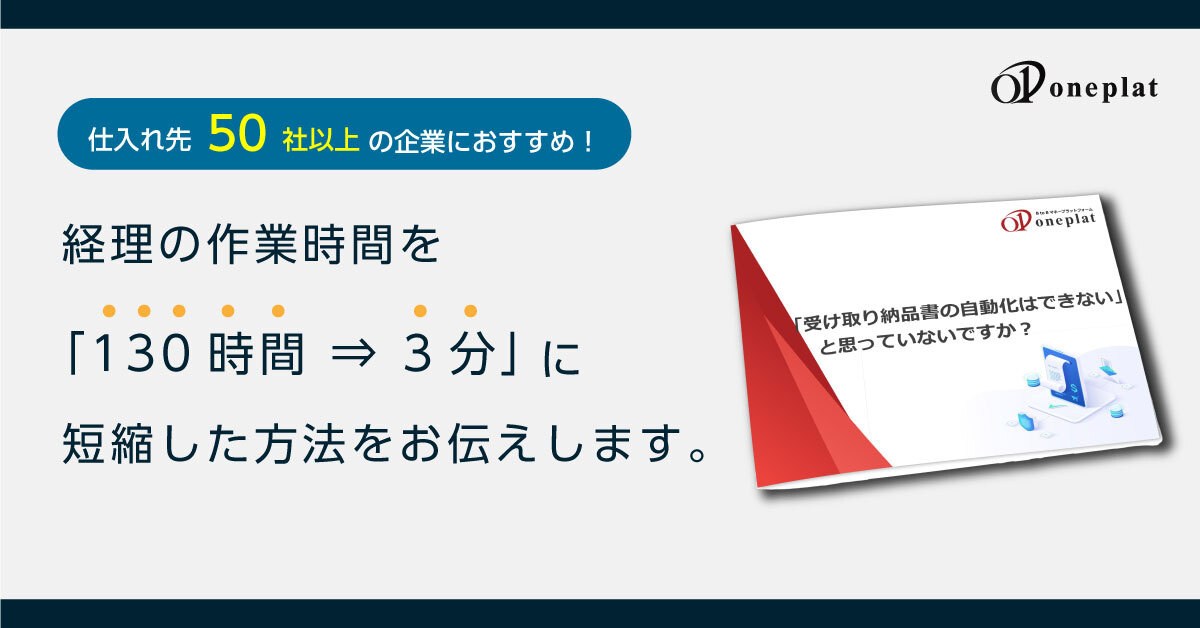請求書は通常1枚で発行されますが、取引内容によっては2枚以上にわたることもあります。
初めて対応する方にとっては、「2枚目以降はどのように記載すればいいのか?」「特別なルールやマナーはあるのか?」といった疑問や不安が生じるかもしれません。
そこで本記事では、請求書が2枚以上になるケースと正しい書き方、注意点について解説します。さらに、請求書発行の手間を減らす方法についても紹介していますので、是非ご参考にしてみてください。
【関連記事】請求書の書き方を項目別に紹介!受領後の流れやトラブル対処法も解説
請求書が2枚になるケースとは?
最初に、請求書が複数枚にわたるケースを解説します。
案件や取引内容が多い
請求書には、取引の詳細を正確に記載することが求められます。
そのため、一度に多数の商品を購入した場合や複数のサービスをセットで提供する場合では、取引内容を請求請求書1枚に収めるのが難しくなります。
商品やサービスの種類が多い
様々な商品をまとめて販売する場合や、複数のサービスを組み合わせて提供する場合には、請求書を分割することは珍しくありません。
長期的なプロジェクトや契約
契約期間が長期に及ぶ場合は、進行状況に応じて段階的に請求を行うことがあります。例えば、卸売業者と小売り業者が年間契約を結び、商品や原料が複数回に渡って供給される場合は、双方の合意のもとで請求が分割されることもあるでしょう。
また、年末年始やゴールデンウィークといった長期休暇では、請求書を分けて発行する必要が生じることもあります。
請求書の記載項目が多い
請求書には、商品名・数量・単価・金額等、多くの情報を記載する必要があります。
さらに、詳細な説明や特約事項を追記する場合や振込先が複数ある場合には、追加のページが必要になるでしょう。
請求書が2枚以上になる場合の書き方
請求書のフォーマットが決まっている企業は多いですが、請求書が複数枚になる場合、書き方のルールはあるのでしょうか。
以下では、請求書が2枚以上になる際の書き方について紹介します。
記載事項は基本的に変わらない
基本的には請求書が2枚以上になったとしても、記載すべき情報に変更はありません。以下のような項目を網羅していれば、問題ないでしょう。
- 取引内容(商品名・サービス名、数量、単価)
- 取引年月日、発行日
- 請求書番号
- 取引先情報(請求先の会社名、担当者名、住所)
- 請求元情報(自社名、住所、担当者名、連絡先)
- 請求金額の合計(小計、消費税)
- 支払期限
- 振込先(銀行名、口座番号、口座名義)
なお、適格請求書では、「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとに区分して合計した金額と適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」も必要です。書き忘れのないようにご注意ください。
【関連記事】インボイス制度で変わることは?適格請求書の書き方・準備を解説
合計金額は1ページのみに記載するのが無難
全体の合計金額(総額)をどこに記載するかについての厳格なルールはありません。しかし、総額を各ページに記載すると誤解や混乱のもとになるため、1ページのみに記載するのが推奨されています。
例えば1ページ目に「合計金額」を明記し、2枚目以降には「1ページ目に記載」と追記すると、分かりやすいでしょう。
小計は各ページに記載する
請求書が2枚以上になる場合は、1ページごとに小計を記載するのが望ましいです。
すべてのページに小計と消費税が書かれていたほうが金額を整理でき、支払側が処理しやすく、請求側も税額計算の誤りを回避することができます。
備考欄にページ番号を明記する
請求書が複数枚にわたるのであれば、備考欄にページ番号を明記しましょう。例えば、1枚目の備考欄に「1/2枚」、2枚目に「2/2枚」と記載すると、受領側も一目で理解することができます。
請求書を2枚以上作成する際の注意点
請求書は通常1枚で発行されることが多いため、取引先によっては2枚目以降があることに気付かず、処理を誤る可能性があります。
取引先にスムーズに処理してもらうために、以下の点を押さえておきましょう。
請求書番号に枝番を付ける
請求書番号は、各請求書を識別し、管理をスムーズにするための番号です。
複数枚にわたる請求書では請求書番号に枝番を付けることで、受取側がすぐに理解しやすくなります。
例えば、1枚目を「INV-20250301-01」、2枚目を「INV-20250301-02」、3枚目を「INV-20250301-03」のように番号を振るとよいでしょう。
送付状に請求書の枚数を明記する
請求書を送付する際は、「送付状(添え状、カバーレター)」を添付するのが基本です。
請求書が複数枚にわたる場合は、送付状に「全〇枚」等の記載を加えることで、取引先の見落としを防ぐことができます。
【関連記事】請求書の送付状はどう書くの?役割と書き方をサンプル付きで解説!
まとめてから封筒に入れる
請求書が2枚以上になる場合は、バラバラにならないよう工夫しましょう。左上をホッチキスまたはクリップで留めるのが一般的です。
また、請求書が複数枚になると、いつも使っているサイズの封筒に収まらないことがあります。その際も封筒を分けるのではなく、大きめの封筒にすべての書類を入れるようにしましょう。
【関連記事】請求書を封筒で送る時はここに注意!封筒の書き方・気をつけたいポイントを徹底解説
角印を押すのは1枚目
請求書には「角印」を押すことが多いですが、複数枚の請求書を発行する場合は1枚目にのみ押印するのが基本です。
2枚目以降には押印する必要はありません。ただし、取引先によっては全ての請求書に押印を求められる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
【関連記事】請求書の押印は不要?義務や根拠は?適した印鑑や押す位置も解説
複数枚の請求書発行は電子化で業務効率化
紙の請求書では印刷・封入・郵送といった作業が発生しますが、請求書が2枚以上になると追加の工数が発生します。
そこで、請求書を電子化することにより、複数枚にわたる請求書でも一括発行できるようになり、業務効率化を図ることが可能です。ここからは、請求書の電子化によって得ることができる様々なメリットをご紹介します。
【関連記事】請求書を電子発行するメリットは大きい!効率的な運用方法と電子発行時の注意点
作成・郵送の手間を削減
請求書を紙で運用している企業では、Excel等で作成したあと印刷し、三つ折り・封函・郵送という作業に時間がかかっているでしょう。
複数枚にわたる場合は記載する情報も増え、クリップやホッチキスで留める作業も発生してしまいます。
しかし請求書を電子化すれば、送付状の「枚数」や備考欄を都度変更する必要もなくなるため、大幅な時間短縮につながります。
【関連記事】請求書の郵送方法|送付状・封筒の書き方と注意点
取引先とのやり取りが迅速化
紙の請求書を郵送すると、取引先に届くまでのタイムラグが発生し、確認や支払い手続きに時間がかかります。
しかし電子化に切り替えればメールやクラウドで送付でき、取引先がすぐに確認可能です。入金処理がスピーディーになり、キャッシュフロー改善にも貢献するでしょう。
請求書の紛失リスクを軽減
紙の請求書では、誤って紛失してしまったり、複数ページの一部が見当たらなくなったりすることも珍しくありません。
しかし、クラウド上で請求書を一元管理することで、紛失のリスクを限りなくゼロに近づけることができます。
送付や開封の履歴が残るサービスもあり、状況を把握しやすい点もメリットです。
【関連記事】請求書の再発行は可能なのか?対処法や日付等のポイントを解説
経理業務の自動化を実現
電子請求書発行サービスはシステムと連携できるものも多く、請求書や納品書の作成を自動化することができます。
さらにインボイス制度や電子帳簿保存法にも対応したサービスを利用すれば、法的要件を満たしつつ効率的な管理が可能です。
発行する請求書の電子化サービスの選び方
請求書の電子化サービスを導入する際は、「余計に手間がかかる」「想定外のコストがかかった」といったトラブルを避けるため、慎重に比較・検討する必要があります。
以下では、特に重視したいポイントを解説します。
最新の法令に対応しているか
多くの電子化サービスは電子帳簿保存法やインボイス制度に対応していますが、すべてのサービスが対応しているわけではありません。
万が一、電子保存要件を満たしていない場合は、税務調査時にトラブルとなる可能性があります。請求書の保存や管理に関する規定が厳しくなっているため、必ず最新の法令に対応できるサービスを選びましょう。
【関連記事】電子化した請求書と納品書の保存期間は?電子帳簿保存法の概要
ソフトやシステムと連携可能か
電子化サービスを導入する際は、既存の業務フローにスムーズに組み込めるかどうかも重要です。
例えば、販売管理システムとの連携が可能であれば、請求書の作成から送付、入金確認までの一連の流れをスムーズに進めることが可能になります。
予算に合っているか
電子化サービスは継続的に利用することになるため、コスト面も慎重に検討する必要があります。
一見安価で利用できるように見えても、初期費用や追加オプションで予算をオーバーしてしまうかもしれません。
基本(月額)料金だけでなく、全体のコストを考慮し、適切なプランを選ぶことが大切です。
oneplatで請求書業務を効率化
請求業務の電子化を進めたいと考えても、「どのサービスを選べばいいのか分からない」と迷ってしまうことも多いでしょう。そんな方におすすめなのが、多くの企業に選ばれている「oneplat(ワンプラット)」です。
oneplatは請求書発行をスムーズにし、経理業務の負担を大幅に軽減できるクラウドサービスです。
以下にoneplatの特徴をまとめましたので、ご参考ください。
請求書をワンクリックで発行
oneplatは、様々な販売管理システムや会計システムと連携可能で、請求書をワンクリックで発行することができます。
また、初めて電子化に取り組む企業でも安心して導入できるよう、手厚いサポートを行っているため、導入から運用までスムーズに行うことが可能です。
インボイス制度・電子帳簿保存法に対応
請求書の電子化を進めるうえで、「法令に対応しているか」は非常に重要なポイントです。
oneplatは、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件を満たした形式で請求書を保存可能です。
税務調査の際にスムーズに対応できるだけでなく、ペーパーレス化を実現し、コストと工数も削減できます。
月額22,000円と低コスト
oneplatの請求書発行サービスは、月額22,000円(税込)です。納品書の発行まで含めたプランもあり、こちらは月額33,000円(税込)で利用可能です。
何社でも、何枚でも追加料金なしで請求書を発行できるため、コストを気にせずに業務を進められます。
また、初期導入費用やサポート費用も一切かからず、優れたコストパフォーマンスで請求書発行業務の効率化を実現します。
まとめ
紙ベースの請求書では印刷や封入等の手作業が発生しますが、請求書が2枚以上になるとさらに作業工数が増えてしまいます。
請求業務の改善を目指すなら、請求書の電子化をおすすめします。
中でもoneplatは、多くの企業に選ばれている請求書発行サービスです。請求書や納品書をワンクリックで発行できるため、請求書が複数枚にわたったとしても手間が増えません。
経理業務の効率化、コスト削減をしたいとお考えのご担当者様は、是非一度、oneplatまでご相談ください。