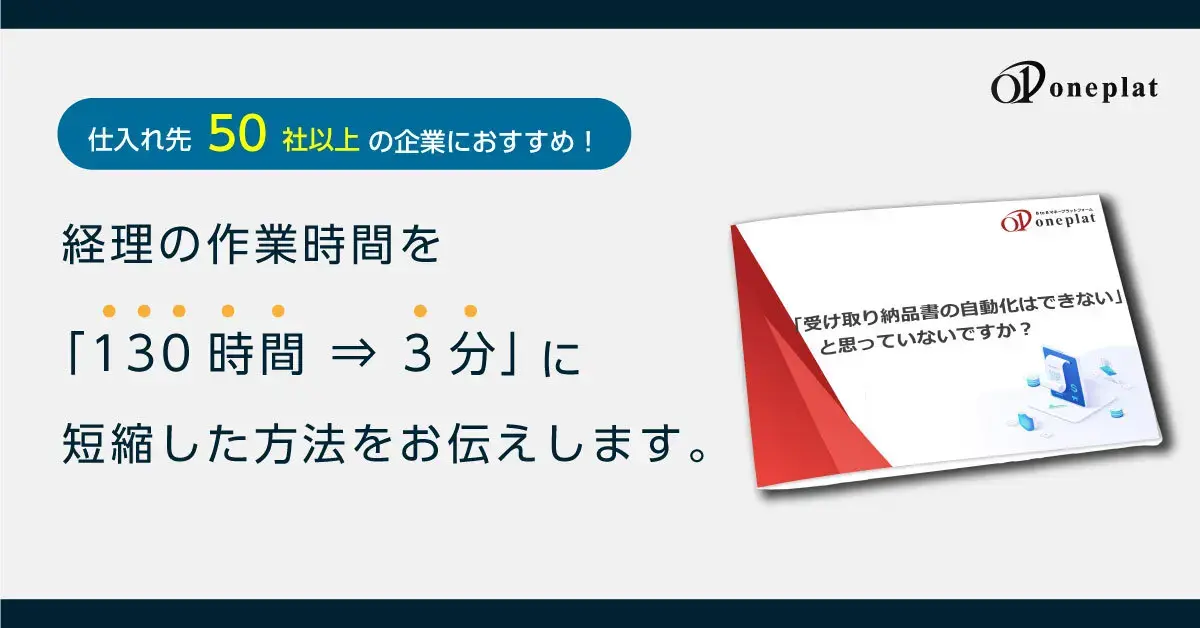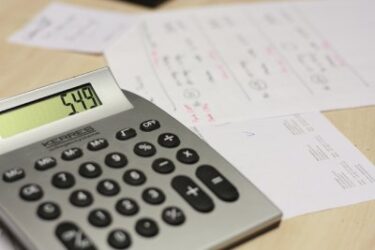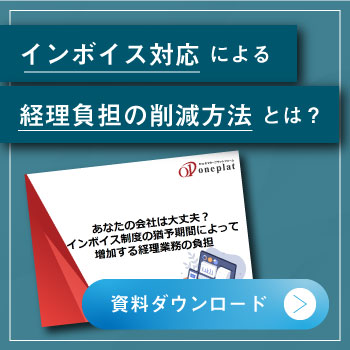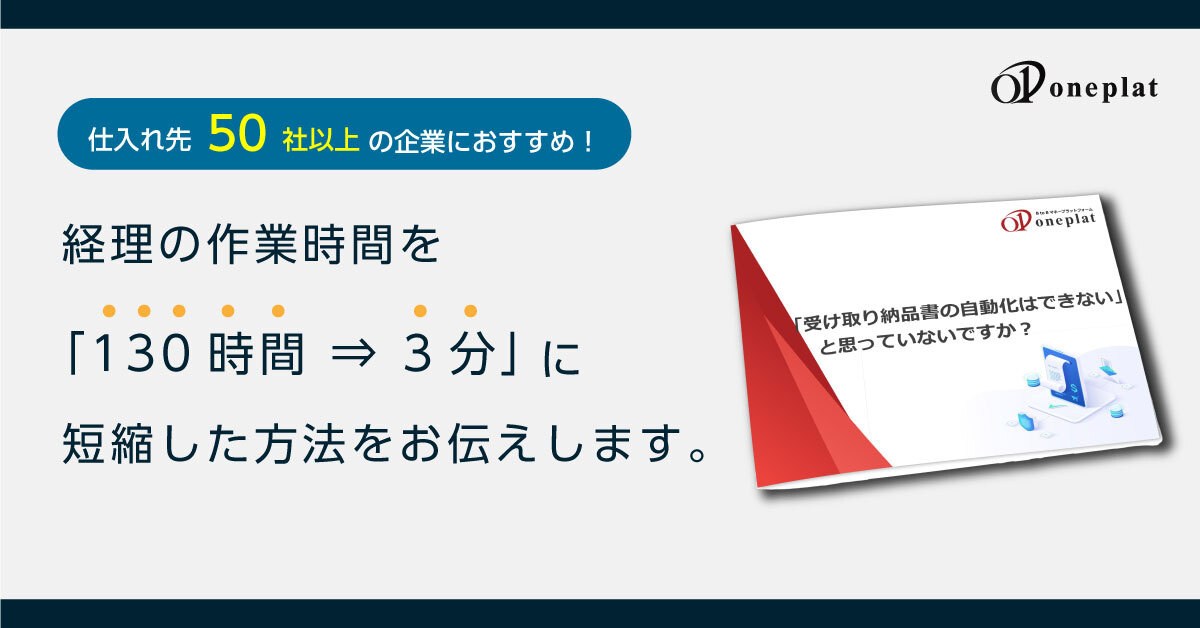日々、多くの取引を行っていると請求と支払いに関するトラブルが発生することもあります。請求書を送付しているにもかかわらず、入金期日までの支払いがなく、連絡もない等、こちらの資金繰りにまで影響を及ぼすようなトラブルが発生しないとは限りません。
では、請求書を無視された場合は、どのように対処するのが良いでしょうか。本記事では、無視される理由や、対処方法、流れ、無視している側に起きる措置等について解説します。
請求書の未払いが発生する理由

多くの企業と取引していると、中には請求書を送付しても入金されないというシーンに遭遇することもあるのではないでしょうか。
本来あってはいけませんが、期日を過ぎても入金がないということも起こり得ます。では、入金しないのにはどのような理由が考えられるか見ていきましょう。
自社のミス
請求書が未払いになっている場合にまず確認すべきなのは、自社側の手続きにミスがなかったかという点です。
- 請求書が送付されているか
- 送付先の住所、担当者や部署に誤りがないか
- 誤った口座番号を記載していないか
これらを確認しないまま取引先に催促をすると、自社の信用を損ねる原因になりかねません。
万が一、自社側にミスがあった場合は速やかに取引先へ謝罪し、正しい請求書を送付しましょう。
取引先のミス
次に考えられるのは、取引先側の確認漏れや入金忘れです。
取引先が多くの企業と取引している場合は請求書の処理が後回しになったり、うっかり支払いを忘れてしまったりするかもしれません。特に月末や決算期は支払い手続きが滞りやすく、期日を過ぎてしまうケースも少なくありません。
このような場合は意図的な未払いではないため、強い口調で催促すると、取引関係に悪影響を及ぼす可能性があります。 相手のミスを責めるのではなく、「支払い期日を過ぎておりますが、ご確認いただけましたでしょうか?」といった、丁寧で冷静な表現を心がけることが大切です。
故意に支払いをしていない
中には、資金繰りの悪化によって、意図的に支払いを遅らせているケースもあります。
例えば、経営状況が悪化し資金が不足している場合や、ほかの支払いを優先している場合などが考えられます。
入金を待っている間に取引先が倒産し、最終的に回収が不可能になるリスクが高まりますので、早めに行動を起こしましょう。
未払いの請求書に対する催促方法
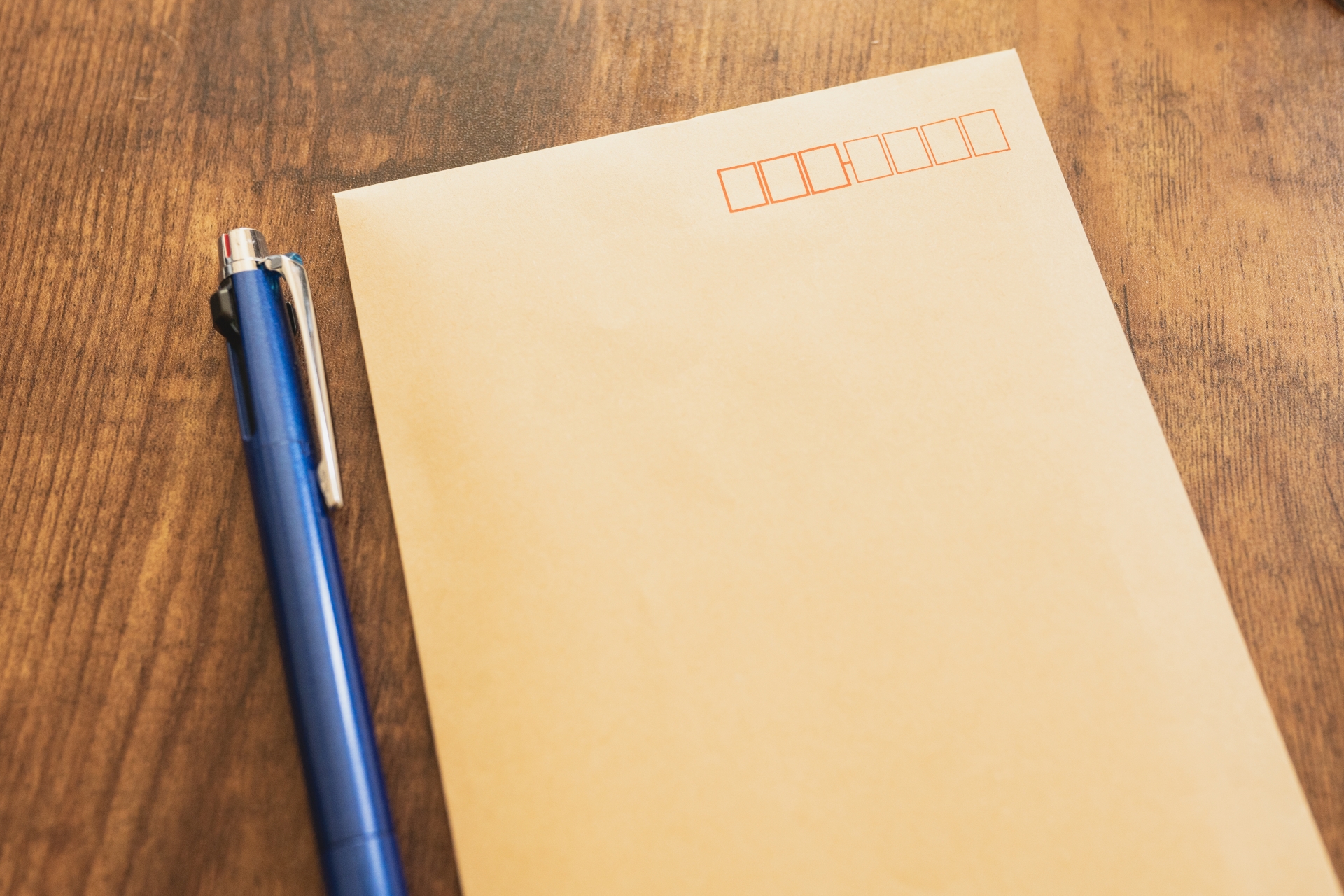
請求書を送付しているにもかかわらず入金がされない場合は、催促状や督促状を送付しましょう。これにより、取引企業へ入金を促すことができます。ここでは、各書類の内容の違いについて紹介します。
催促状
期日後も入金がなければ、まず催促状を送付します。故意ではない遅延であるとも考えられますので、一般的に強い文言は控えた内容文で送ることが多いでしょう。
督促状
催促状を送付しても反応がない場合に、督促状を送付します。売掛金回収の遅延は自社の資金繰りにも影響を及ぼしますので、より速やかな対応を促すために、強い文言の内容で送ることが多いでしょう。
何度か連絡した後に送るため、督促状の方がより強い要求の書類とされています。入金がない理由は確認漏れや入金忘れ等、故意ではない場合もありますので、1度目は催促状にて促し、それでも反応がない場合は、督促状で強く要求するというイメージです。
内容証明
場合によっては上記対応後も、入金が行われないということもあります。このような状況の対策としては、内容証明郵便で督促状を送付することをおすすめします。内容証明とは、送付した年月日や内容、送付した事実を証明するものです。また、入金の時効が2年間からプラス半年延長されます。
この内容証明自体に強制力があるわけではありませんが、送付することで法的手段に訴えることもあるという強い意思表示にもなり、心理的な効果も期待できます。また、内容証明は裁判において証拠として提出することも可能です。
催促状、督促状の送り方

貸倒れにより売掛金回収が困難になることは、自社にとって大きな損失となります。資金繰りの悪化や自社の支払いにも影響を及ぼしかねません。それを回避するために、未対応の取引企業に対しては、催促状、督促状を送付します。ここでは、送付までの流れを紹介します。
①自社に何か問題がないか確認する
期日を過ぎても入金がない場合は、取引企業に入金を促す必要がありますが、その前に、まずは自社側の対応に問題がなかったか確認しましょう。もしかすると、請求書の送付先や記載した振込先に誤りがあるかもしれません。書類自体の送付忘れ等も考えられるでしょう。
自社側で発生したミスであるにもかかわらず催促してしまえば、トラブルや信用の低下に繋がってしまうこともありますので、必ず確認を忘れずに行いましょう。
②メールや電話で連絡を取る
自社側でのミスではないことの確認が取れたら、取引先にメールまたは電話で連絡を入れましょう。ここで、なぜ入金が滞っているのか説明を求めます。その事情が納得できるものかよく検討した上で、期日を再設定します。
急ぎの回答が必要な場合は、電話で連絡することもありますが、記録を残しておくという点ではメールで連絡する方が良いかもしれません。
③催促状を作成し、送付する
電話やメールで連絡を取り、期日を再設定したにもかかわらず入金がされない場合に送付しましょう。正式な書類であることの証明として、角印を押印することをおすすめします。また、強制力のある書類ではありませんので、電話やメールで連絡した内容のリマインダーのようなイメージで利用すると良いでしょう。
④督促状を作成し、送付する
その後も連絡がない場合は、督促状を送付しましょう。こちらはより強い文言の内容文で送付します。また、今後も未払いの可能性があるということを頭に入れて、内容証明郵便で送付しておくと良いでしょう。
これにより、年月日や内容、送付した事実を証明でき、書類が法的効力を持ちます。万が一、裁判に発展したときには証拠書類として提出することも可能となるため、覚えておきましょう。
督促状って何を書けばいいの?

ここでは、記載する一般的な内容について紹介します。
・発行日:発行日や送付日を記載します。これにより、送付先から連絡や対応があった際に、書類の指定がしやすくなります。
・宛先:取引企業の名前を記載します。支店や部署がある場合は、そちらまで記載しましょう。
・差出人:自社の会社名や部署、担当者の名前を記載します。また、上役の記載と捺印も忘れないようにしましょう。
・表題:強い要求であるため、表題もシンプルに「督促状」としておくとよいでしょう。雰囲気を和らげたい場合は、「お支払いのお願い」等と変更しても良いです。
・支払要求:該当する取引内容や支払額、期日、予定日の言及等を具体的に記載します。内容に誤りがあればトラブルのもとになりますので、しっかり確認してから送付しましょう。
・法的措置の連絡:送付後、期日までに入金がされなかった場合は、法的措置を検討することを記載しておきます。今後、検討している対応の流れについて言及しておくと良いでしょう。
逆に請求書を無視するとどうなる?

ここでは、取引企業側つまり請求を受けている側の対応や、未払いによる影響について紹介します。支払いが可能であるのにもかかわらず無視していると、企業の信用が下がることはもちろんですが、差し押さえ等の法的措置を取られることもありますので、故意な未払いは避けましょう。
督促状が届き、最終的にはブラックリストや差し押さえになる
請求に対する支払いを期日までに済ませないと、督促状が届きます。そしてこの書類は、法的措置に出る前の最終勧告だということを覚えておきましょう。その後も未払いでいると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。これがいわゆるブラックリストというものです。
その後は、裁判所への申し立てにより、差し押さえの手続きに入る旨の連絡が届きます。この際に届く支払督促に対し、2週間以内に督促異議申立書を提出しなければ、差し押さえが強制執行されますので注意しましょう。
督促状が届いたら詐欺ではないかを確認しすぐに支払おう
督促状が届いたら、直ちに支払いを済ませることが大切です。ただし、その際に一つ注意点があります。それは、架空請求等の詐欺ではないか確認するということです。まずは、取引の事実があるか確認を行い、詐欺ではないことがわかってから速やかに入金しましょう。
請求書の未払いリスクを軽減する方法
以下では、未払いを防ぐための方法をご紹介します。
与信管理を徹底する
与信管理とは、取引先の支払い能力や経営状況を調査し、安全に取引ができるかを判断することを指します。特に新規取引の際には、信用調査を行っておくと安心です。
ただし、与信管理は一度きりで終わらせず、定期的にチェックしましょう。
もし取引先の信用状況が悪化している兆候が見られた場合は、取引条件の見直しや前払いの導入など、早めに対策を講じましょう。
業務フローを見直す
請求書の未払いが発生する原因は、取引先の問題だけではなく、社内の業務フローに課題がある場合も考えられます。
例えば経理部門と営業部門の連携が不十分だと請求書の送付ミスや確認漏れが発生し、支払い遅延を引き起こすかもしれません。
社内の連携を強化することで請求業務の精度を高めることができ、未払いの防止にもつながるでしょう。
電子化サービスを導入する
電子化サービスを導入することで請求書の作成や送付が自動化されるため、発行ミスや送付漏れがなくなります。取引先が請求書を紛失した場合でも再発行が簡単にできるため、迅速な対応が可能です。
また、支払期日が近づくとアラートが自動で送信されるため、取引先がうっかり支払いを忘れることを防ぐこともできます。
請求書の未払いを回避できるだけでなく、請求業務全体の効率化も叶うため、是非ご検討ください。
まとめ:請求書を無視された場合、した場合の対処法を知っておこう

本記事では、請求書が無視される理由や、対処方法、流れ、無視している側に起きる措置等について解説しました。請求に対する未払いは、トラブルの原因になりますので、送付された側の企業は、速やかに入金を済ませましょう。
また、請求側は未払いの状態が続くと自社の資金繰りにも影響しますので、適切な方法で入金を促しましょう。それでも未払いが続くようであれば、法的措置に出ることも検討しておくと良いでしょう。