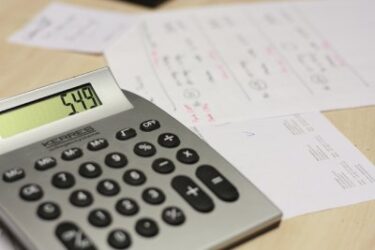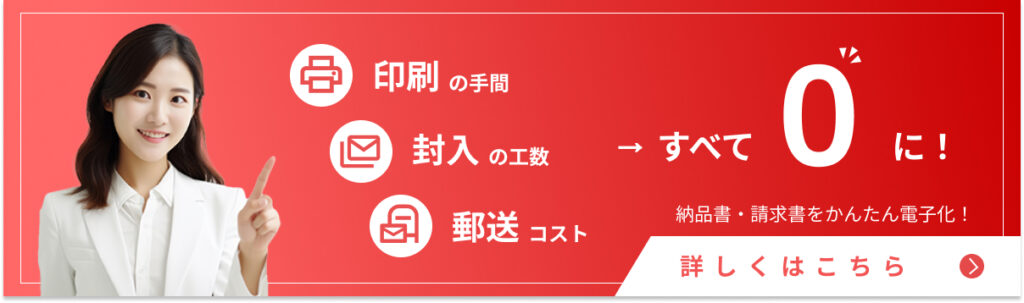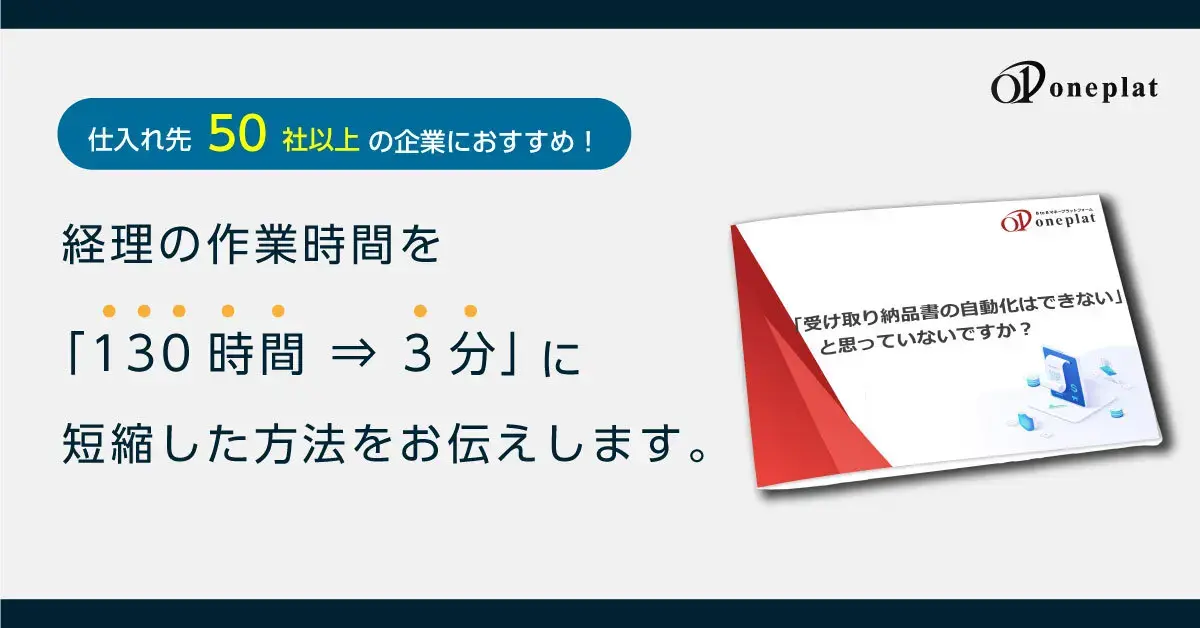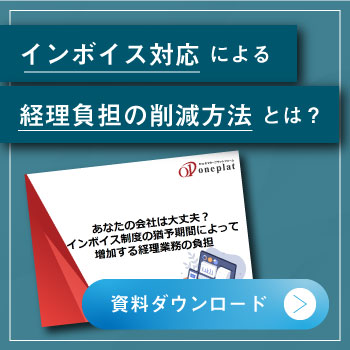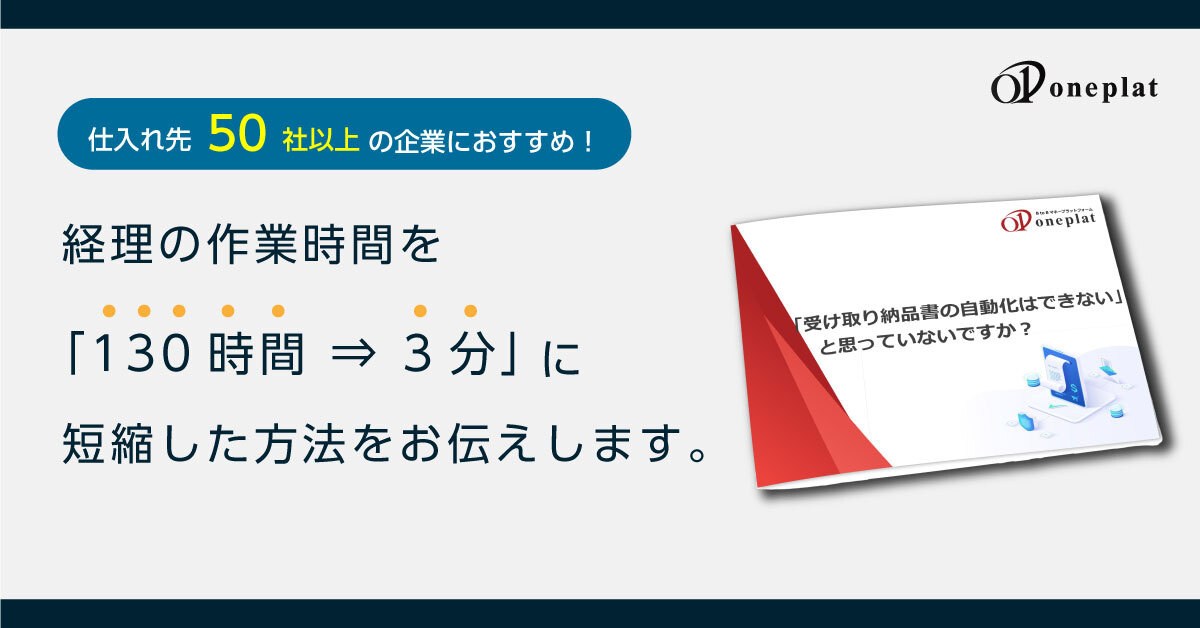近年、多くの企業で業務のDXが進められています。そのなかで「請求書の電子化に興味はあるが、具体的なメリットがわからない」「導入してみたいが、どのような方法があるのか分からない」「電子化によるリスクが心配。事前に注意点を知っておきたい」という企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、請求書を電子発行することのメリットや注意点、具体的な運用方法について解説しています。
請求書発行業務の効率化とコスト削減を実現する方法もご紹介しますので、ぜひご参考ください。
また、受取請求書の電子化については以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】受け取る請求書を電子化するメリット、義務化要件と効率的な電子保存(管理)方法もあわせてご紹介
請求書発行を電子化するメリット
紙の請求書から電子請求書へ移行することで業務の効率化を図ることができます。以下に、具体的なメリットをご説明します。
郵送コストを削減できる
請求書を印刷する場合、紙やインクの使用により費用が発生するだけでなく、郵送するための印刷や封筒の準備、郵便局への持ち込み作業などの労力もかかります。特に、大量の請求書を発行する企業にとっては、このような費用・労力の負担が課題となっているのではないでしょうか。
請求書の発行を電子化することで印刷の必要がなくなるため、紙やインク、封かんや切手代などの費用を削減することができます。また、請求書の送付はメールや請求書発行システムから行うことができるため、これまで郵送にかかっていた時間・労力を軽減し業務の効率化にも繋がります。事前に送付先の氏名やメールアドレスを登録しておくことで、一括で請求書をメール送付するサービスもあります。このようなサービスを活用することで、より業務負担を軽減することが可能です。
【関連記事】【2024年10月実施】郵便料金の値上げ内容を解説|納品書・請求書郵送への影響とコスト削減方法をご紹介
修正・再発行が容易になる
紙の請求書では、金額や単価、数量に誤りがあった場合、発行し直すのが原則です。このため、請求書を修正する場合、新しい請求書を作成し訂正前のものと区別して保存する手間が増えますが、電子請求書に切り替えることで、修正や再発行が格段に簡単になります。
例えば、電子請求書システムでは、誤りを修正した後、ボタン一つで新しい請求書を発行し、送信することが可能です。これにより、再発行にかかる時間と労力が大幅に削減されます。
押印のために出社する必要がなくなる
請求書への押印は法的な義務ではありませんが、慣習として押印を求める企業も多くあります。このため、担当者が押印のためだけに出社しなければならないケースも少なくありません。
しかし、電子請求書を導入すれば、現場や外出先からでもインターネットを通じて簡単に請求書の発行・押印が可能になります。例えば、出張中の担当者が急ぎで請求書を発行しなければならない場合でも、電子請求書であればその場で対応が可能です。
特にテレワークを推進したい企業にとって、このメリットは非常に大きいと言えます。
【おすすめ関連資料】経理業務をテレワーク化するためには
電子請求書を発行する際の注意点
電子請求書へ切り替える際のデメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 導入・運用コストがかかる
- 電子帳簿保存法への対応が必要
- 取引先からの了承が必要
注意すべきポイントを事前に確認しておきましょう。
導入・運用コストがかかる
請求書を電子化するためにシステムやツールを導入する場合、初期費用や月額費用が発生します。基本料金に加えて、カスタマイズに追加料金がかかる場合もあります。
さらに、従業員への教育コストも無視できません。新しいシステムの操作方法や運用ルールを習得するには一定の時間が必要です。特に、ITに不慣れな従業員が多い場合、この教育コストは高くなる傾向にあります。
そのため、システム・ツールを選定する際は「全体的なコスト」と「誰でも使える操作性」を重視すると良いでしょう。
例えば、電子請求書発行ツールであれば低料金で提供されているものが多く、直感的なインターフェースを持つため、導入や運用のコストを大幅に削減できます。
電子帳簿保存法への対応
請求書を電子発行する場合、電子帳簿保存法への対応が必要です。電子帳簿保存法とは、帳簿や書類をデータで保存する際の要件を定めた法律です。
発行側は任意ですが、パソコンで作成した請求書はデータとしてそのまま保存します。
注意したいのは、受領側は電子取引のデータ保存が完全義務化されているという点です。
例えばメールでPDFの請求書を受け取った場合、2022年に施行された電子帳簿保存法の改正では、2年間の宥恕(ゆうじょ)措置により紙に印刷して保存することも可能でした。しかし、2024年1月に宥恕措置が廃止されたため、今後取引先にはデータで受け取った書類をそのまま保存してもらう必要があります。
加えて、保存する際には「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。そのため、電子請求書を送付する前に、取引先が対応できるかどうかを事前に確認したほうが良いでしょう。
【関連記事】電子帳簿保存法改正 猶予期間・請求書電子化の義務化への準備を
取引先からの了承が必要
先述した通り、請求書を電子化する際には、受け取る側の企業も電子帳簿保存法を遵守する必要があり、そのための準備が求められます。
新しい業務フローを構築するにはコストがかかるため、すべての取引先が電子請求書に対応してくれる訳ではありません。また、社内の規程により、紙の請求書でなければ受け付けない企業も存在するでしょう。
そのためすべての請求書を電子化することは難しく、一部の取引先とは紙でやり取りを残ることも視野に入れる必要があります。
【関連記事】請求書の電子化における案内状のポイントは? テンプレートも紹介
電子請求書の効率的な運用方法
紙の請求書から電子請求書へ切り替える方法はいくつか存在しますが、特に業務効率化に繋がる方法をご紹介します。
メールにファイルを添付する
電子化の手軽な方法として、請求書をPDF形式で作成し、メールに添付して送信する方法があります。紙の請求書とは異なり、印刷や郵送の手間が省けるため、迅速に請求書を送信することができます。また、PDFファイルは広く利用されているフォーマットであり、発行側も受領側もほぼ問題なく対応できるため、導入のハードルが低い点もメリットです。
しかし、メールを利用する方法では、請求書作成の手間は省けません。多くの企業はExcelやWordを利用して請求書を作成していますが、この作業は依然として手動で行う必要があります。効率化を図りたい場合は、システム連携や専用ツールの導入も視野に入れてみましょう。
クラウドストレージにアップロードする
請求書をWebサイトにPDFやPNGなどのファイル形式でアップロードし、取引先にダウンロードしてもらう方法もあります。この方法は、請求書を個別に送付する手間が省けるため、特に大量の請求書を発行する企業にとって便利です。
具体的には、取引先ごとに専用のダウンロードページを用意します。
取引先は自社専用のページにアクセスして請求書をダウンロードするだけで済むため、発行当日に請求書を受け取ることができます。また、過去の請求書もオンライン上で保管・管理できるため、取引履歴の確認も容易です。
ただし、インターネットを利用するため、接続トラブルが発生すると閲覧やダウンロードができなくなるリスクが考えられます。さらに、情報漏洩やデータの改ざんリスクも存在します。セキュリティ対策として「アクセス制限の設定」「暗号化通信」などを行う必要があるでしょう。
社内システムと連動させる
社内システムと連動させることで、請求書発行業務の効率化と正確性の向上が実現します。
例えば、販売管理システムと連携して、受注情報から自動的に必要な情報を取り込むことで、瞬時に電子請求書として発行することができます。
これにより、手作業によるミスを未然に防ぎ、確認作業の手間も大幅に削減されます。
しかし、システム連携やカスタマイズには専門的な知識が必要なため、外部に依頼する場合は高額な費用が発生することもあります。要件次第では予算を大幅に超える可能性もあるため、潤沢な予算がない場合は他の方法を検討したほうが良いでしょう。
電子請求書発行サービスを利用する
電子請求書発行サービスとは、請求書の作成、発行、保存に特化したサービスです。サービスによって機能の詳細は異なりますが、請求書の自動作成や送信機能が備わっているため、経理や総務などのバックオフィス業務の工数を大幅に削減できます。
ただし、電子請求書発行サービスは月額料金を支払うサブスクリプションタイプが多く、導入費用が必要になるサービスもあるため、選定する際にはコストの確認が重要です。
また、請求書の発行枚数や利用ユーザー数によって料金が変動する場合もあり、予算管理が難しくなる可能性があります。このため、固定料金で提供されるサービスを選ぶことをおすすめします。
低コストで電子請求書の一括発行を始めるなら「oneplat(ワンプラット)」
出費を抑えつつ請求書の電子化を進めたいなら、コストパフォーマンスに優れた電子請求書発行サービスを推奨します。その中でも、多くの企業に選ばれているのが「oneplat」です。
ここからはoneplatの特徴をご紹介しますので、ぜひご参考ください。
月額22,000円、初期費用0円
oneplatの利用料金は月額22,000円(税込)です。取引先が増えたり、発行枚数が増えたりしても追加料金はかかりません。
初期導入費用やサポート費用も一切不要です。予算管理がしやすく、安定して利用することができます。
販売管理システム・会計システムと連携可
oneplatは各種システム連携に対応しており、請求書をワンクリックで発行可能です。
例えば「弥生販売」からCSVデータを取り出し、oneplatに連携するだけで、請求書の一括発行作業が簡単に行えます。
この連携により、手作業のミスを防ぎ、作業効率を大幅に向上させることが可能です。
電子帳簿保存法・インボイス制度に対応
電子帳簿保存法により、電子取引のデータ保存が義務化されました。発行側・受領側双方が細かい要件をクリアしなければいけませんが、oneplatは要件を満たした形で請求書の発行と保存が可能です。
さらに、2023年10月に開始したインボイス制度にも対応しているため、安心してご利用いただけます。oneplatなら法令遵守と業務効率化を両立させることができます。
まとめ
本記事では、請求書を電子発行するメリットや注意点、効率的な運用方法について解説しました。
紙の請求書から電子請求書へ切り替えることで、コスト削減や出社不要といった多くの利点が得られます。しかし、導入には初期費用がかかり、発行側・受領側ともに電子帳簿保存法に対応する必要があります。
運用方法としては、メールにファイルを添付する方法や、取引先にクラウドストレージからダウンロードしてもらう方法などがありますが、おすすめは電子請求書発行サービスの利用です。
特に「oneplat」は、月額22,000円(初期費用0円)と手ごろながら、販売管理システム・会計システムと連携でき、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しているため、多くの企業に選ばれています。
詳細は以下のページにて紹介しておりますので、ぜひご覧ください。