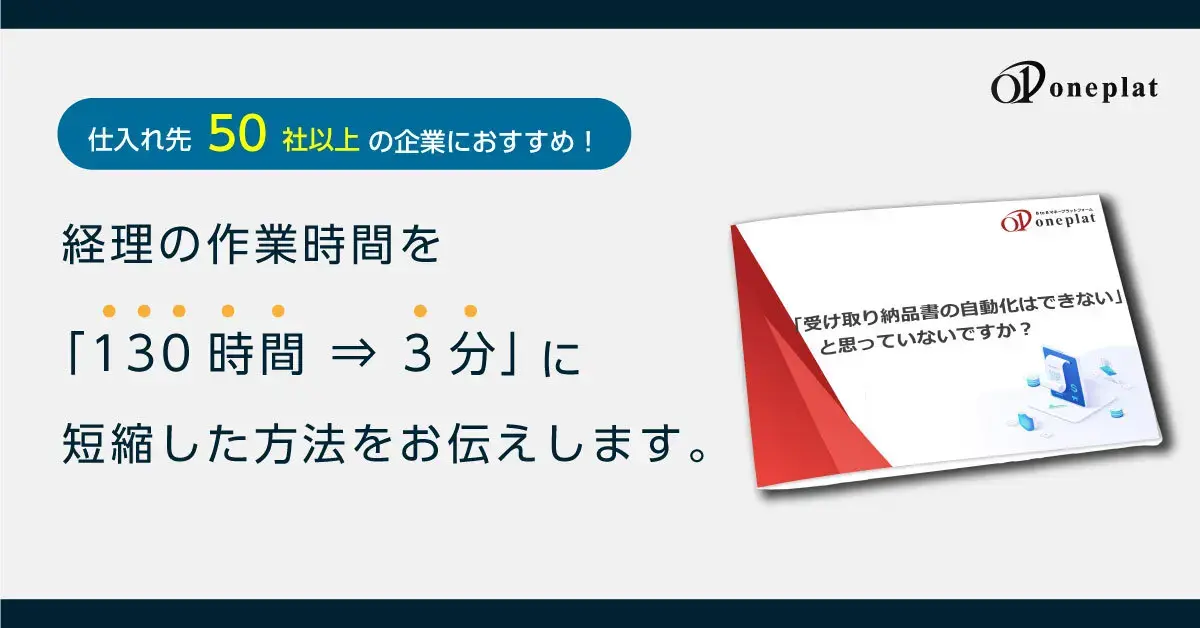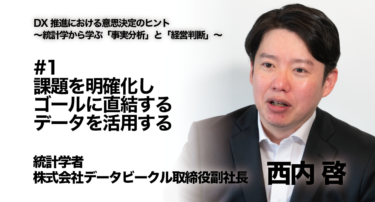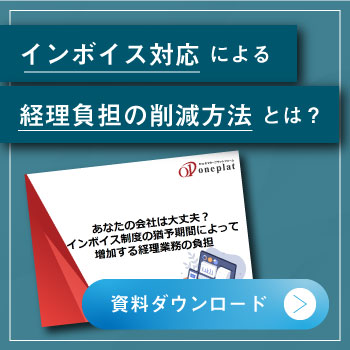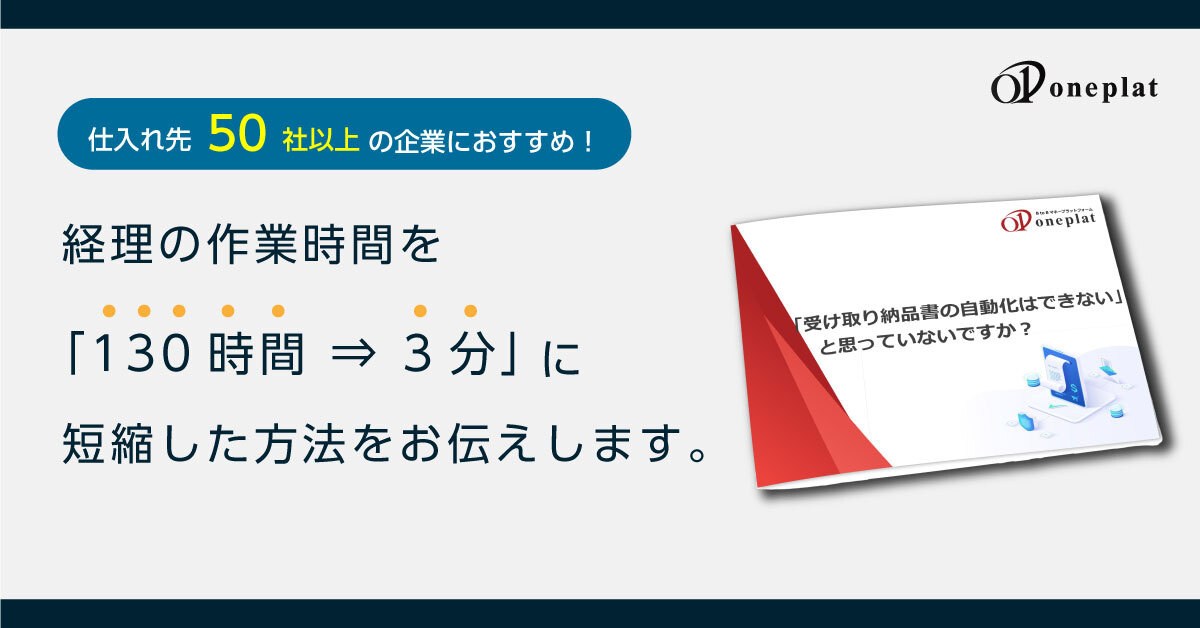2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正や、2023年10月に施行されたインボイス制度など、納品書をはじめとした帳簿書類の電子化を行う必要性が高まっています。
しかし、「納品書の電子化を行ってもいいのかわからない」「電子化や法律に詳しくないけれど、簡単に納品書の電子化を行いたい」「システムを導入するなら、業務効率が上がるシステムを導入したい」などの、悩みや問題を抱えている企業も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、納品書の電子化は可能です。また、納品書の電子化を簡単かつスムーズに行いたいなら、クラウド型の納品書受領システムの導入がおすすめです。
この記事では、以下の流れで、
・納品書の電子化とは
・納品書受領システムを導入するメリットとは
・納品書受領システム導入による注意点とは
・納品書受領システムの選び方とは 納品書の電子化から納品書受領システムの選び方について、ご紹介します。
請求書の電子化についてご興味がある方はこちらの記事もご覧ください。
【関連記事】受け取る請求書を電子化するメリット、義務化要件と効率的な電子保存(管理)方法もあわせてご紹介
納品書の電子化とは

電子化とは、これまで紙でやり取りしていた書類を、PDFやクラウドシステムを活用してデータとして作成・管理することを指します。
近年、多くの企業が請求書の電子化を進めていますが、「納品書も電子化すべきなのか?」「データ保存して、税務調査で指摘されないのか?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
まずは、納品書の電子化が法的に問題ないのか、また電子化が求められる背景について解説します。
納品書の電子化とは
帳簿書類等の保存期間 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注1)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」より
ですが、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」、通称「電子帳簿保存法」で定められた条件を満たしている場合に限り、紙で保存していた国税関係帳簿書類のデータ保存が認められるようになりました。
そのため、納品書の電子化は税法上で認められています。
【関連記事】納品書の電子化にまつわる法律とデータ化する方法を解説
納品書の電子化が求められる背景
2021年12月までは、デジタルで受領した納品書を印刷し保存することが許可されていました。しかし、2022年1月に施行された「電子帳簿保存法」の改正により、2024年1月からはデジタル形式で受け取った文書(電子取引文書)の印刷保存が許可されなくなります。
さらに、2023年10月1日からインボイス制度が導入され、適格請求書の写しまたは適格請求書のデータを保存する義務が発生しました。
納品書を適格請求書とする場合は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければいけません。
そのため、これまでデジタル形式で受け取った納品書を印刷し、紙で一元管理していた企業は、紙とデジタルを併用することになるため管理が煩雑になります。特に、紙で受け取る納品書の枚数が多い企業は、デジタル形式で受け取った納品書を印刷し、紙で一元管理していたのではないでしょうか。
また、紙とデジタルの両方で保存を行うと、管理が煩雑になるだけでなく、データの検索も困難となり、整合性の確保が難しくなるという課題が生じます。これにより、アクセス性と効率性が著しく低下する可能性があります。
このような背景から、納品書をはじめとする取引文書をシステムで一元管理することが、企業にとって最も効率的な手法であると考えられています。この流れに遅れをとらないためにも、一刻も早く電子化に取り組むことが重要です。
【関連記事】指定納品書(指定伝票)の必要性~廃止と電子化のすすめ
納品書の発行側と受け取り側の保存要件の違い
納品書の保存要件は、発行側、受け取り側それぞれ「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引の電子データ保存」という3つの保存要件によって違いがあります。
・発行側
電子帳簿等保存:
自身ではじめから一貫してパソコンなどで作成した納品書の控えは、任意で電子データのまま保存できます。
スキャナ保存:
紙で発行した納品書の控えは、一定の保存要件のもとスマートフォンやスキャナで読み取り、任意で電子化して保存することが可能です。
具体的には、以下の要件が挙げられます。
- 書類を作成後、おおむね7営業日以内にスキャンすること(早期入力方式)
- タイムスタンプを付与すること
- 訂正・削除を確認することができるシステムを使用すること
- 解像度は200dpi相当以上
- カラー画像は赤・緑・青の階調が256以上(24ビットカラー)であること
- 帳簿との関連性がわかるようにすること
- 14インチ以上のカラーディスプレイとカラープリンターを用意すること
- 操作説明書やシステム概要書などを備付けること
- 取引年月日、取引金額、取引先名で検索できること
電子取引の電子データ保存:
電子データで送付した納品書の控えは、紙に出力するのではなく電子データのまま保存しなければならないと義務付けられています。印刷して紙で保存することは認められていませんのでご注意ください。
・受け取り側
電子帳簿等保存:
該当の要件はなし
スキャナ保存:
相手先から紙で受領した場合、一定の保存要件のもとスマートフォンやスキャナで読み取り、任意で電子化して保存することが可能です。
具体的には、以下の要件が挙げられます。
- 書類を受領後、おおむね7営業日以内にスキャンすること(早期入力方式)
- タイムスタンプを付与すること
- 訂正・削除を確認することができるシステムを使用すること
- 解像度は200dpi相当以上
- カラー画像は赤・緑・青の階調が256以上(24ビットカラー)であること
- 帳簿との関連性がわかるようにすること
- 14インチ以上のカラーディスプレイとカラープリンターを用意すること
- 操作説明書やシステム概要書などを備付けること
- 取引年月日、取引金額、取引先名で検索できること
電子取引の電子データ保存:
電子データとして受領した場合、電子データのまま保存しなければならないと義務付けられています。
以上のように、発行側、受け取り側ともに、保存形式によって電子化が義務付けられている場合と任意の場合があるため、注意が必要です。
【関連記事】納品書の役割や発行側の注意点、受領後の流れをわかりやすく解説
受け取る納品書を電子化するメリット

受け取る納品書を電子化するメリットとして、以下の5つが挙げられます。
- 納品書を一元管理できる
- 原本管理の手間・コストが省ける
- 迅速にやり取りできる
- セキュリティが強化される
- テレワークを推進できる
具体的に解説していきます。
納品書を一元管理できる
納品書を紙で管理していると、確認や入力の手間がかかり、業務負担が増大します。
特に、支店から本部へ納品書を送付して保管している場合は、過去の書類を参照したくとも迅速な対応は難しいでしょう。
しかし、納品書を電子化することで一元管理が可能になり、業務の効率化が実現します。例えば、必要なデータをすぐに検索・閲覧できるようになり、確認作業のスピードが向上します。
また、紙の納品書を手作業でシステムに入力する必要がなくなるため、入力ミスや計算ミスのリスクが減り、作業精度が向上するでしょう。
原本保管の手間・コストが省ける
納品書を電子化することで、納品書の原本を紙で保管することで現在必要となっている紙代やトナー代、印刷代など、紙での出力に伴うコストを削減できます。
また、紙の納品書を保管するためのスペースを確保する手間や、ファイリングの手間もかかりません。
現状で扱っている紙の納品書が多いほど、手間やコストの削減をより強く実感できます。
迅速にやり取りできる
紙の納品書の場合は、取引先が印刷・封入・発送し、受け取った側が開封するまでに時間がかかります。
もし内容にミスがあり再発行が必要になれば、再度印刷・発送の手続きを経るため、請求処理や支払いにも影響を及ぼすでしょう。
一方で、納品書を電子化すれば、メールやクラウド上で即座に送受信が可能になります。
パソコンやスマートフォンからすぐに内容をチェックできるため、確認・承認のスピードが向上します。
金額の誤差などがあった場合でも、データの修正や再送信が簡単にできるため、スムーズに対応可能です。
セキュリティが強化される
納品書には商品や金額だけでなく、従業員や取引相手の個人情報が含まれることもあります。
納品書を紙で保管する場合、簡単に持ち運べるため、不正な持ち出しやコピーのリスクが高まります。鍵付きの机やキャビネット、監視カメラ、金庫など等のセキュリティ対策を講じても、完全に防ぐことは難しいでしょう。
しかし、納品書の電子化により、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。
例えばアクセス権限を付与したり、パスワードを設定したりすることで、担当者以外の閲覧を制限することが可能です。
テレワークを推進できる
紙の納品書を扱う場合、担当者はオフィスに出勤して書類を確認し、承認する必要があります。しかし、納品書を電子化することで、経理担当者が出社しなくても自宅や外出先から納品書を処理できるようになります。これによりテレワークの推進につながります。が可能となり、働き方の柔軟性が向上します。
また、後述するクラウド型の納品書受領システムのなかには、受け取る請求書や支払い通知書などの帳票類も電子化することが可能なタイプもあります。自社の業務に合った納品書受領システムを活用することで、より働き方の柔軟性が向上するでしょう。
【おすすめ関連資料】経理業務をテレワーク化するためには
受け取る納品書を電子化する方法
納品書の電子化を行う方法はいくつかありますが、大きく分けて4つの選択肢が挙げられます。
- スキャンして保存する
- 自社でシステムを構築する
- OCRで変換する
- 納品書受領システムを導入する
スキャンして保存する
紙の納品書をスキャナーや複合機、スマートフォン、デジタルカメラで撮影し、画像データとして保存する方法です。
ほかの電子化手段と比べて導入コストが低く、手軽に始められるため、中小企業や個人事業主に適した方法と言えます。
ただし、スキャナ保存を適用するためには、電子帳簿保存法の要件を満たすことが必須です。具体的には、「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められます。
対応したシステムを導入しない場合は、データ検索が可能な状態にするための工夫が必要になります。例えば、「取引年月日・取引金額・取引先名をファイル名に含める」、または「Excelなどで索引簿を作成する」といった作業を業務フローに追加しなければいけません。
また、適切に運用するためには、社内でルールを統一し、マニュアルを作成して従業員に周知徹底することが重要です。
保存要件を満たせていなければ、税務調査で問題視されるリスクがあります。隠蔽とみなされた場合は通常の追徴課税(35%)に加えて、さらに10%の重加算税が課されるため、ご注意ください。
参照:国税庁 電子帳簿保存法が改正されました
自社でシステムをつくる
2つ目は、納品書を電子化するシステムを自社で構築する方法です。自社でシステムを開発することで、企業固有のニーズに合わせて細かいカスタマイズが可能となります。これにより、業務プロセスに完全に合致したシステムを構築できるため、業務の効率化を最大限に進めることが可能です。
しかし、自社でシステムを構築するには、エンジニアの確保や開発費、サーバー費用など、莫大な初期投資が必要となります。また、企業によっては、開発から導入までに長い時間がかかることがあります。特に、コアビジネスから離れたシステム開発にリソースを割くことは、事業の成長に影響を与える可能性があります。そのため、こちらもあまり現実的な選択肢だとはいえません。
OCR技術を活用する
OCRはOptical Character Recognition/Reader(光学的文字認識)の略で、活字や手書きのテキストの画像を専用のスキャナで読み取り、文字データに変換するソフトウェアであり、紙の文書をデジタルデータに変換する際に注目されております。
しかし、大量の帳票を処理する場合、OCRは各帳票の特性を正確に捉えるのに苦労します。特に、取引の詳細が異なり、それぞれ発行される企業ごとに独自のフォーマットやレイアウトを持っている納品書の場合、OCRの認識精度は著しく低下します。その結果、処理後にデータが正しく読み取れているか紙とデータの目視確認や修正により、人的リソースの増加に繋がってしまい、、業務の合理化につながるとは限らないことには注意が必要です。
OCRについて、詳しくはこちらの記事で解説をしております
【関連記事】OCRとは?注目されている背景や得意領域や導入の上での注意点まで解説!
外部の納品書受領システムを導入する

外部のシステムであれば、すでに開発されたシステムを使って、インボイスや改正電子帳簿保存法といった最新の制度に簡単に対応できるメリットがあります。また、自社でシステムを開発・維持することに比べて、初期投資費用や維持管理にかかるコストを削減する効果が期待できます。
さらに、クラウド型のシステムであれば、どこからでもシステムにアクセスが可能になり、電子化された納品書を確認できるため、テレワークにも対応できます。
まとめますと、コスト効率と業務の質の両方を同時に改善する有効な戦略として、「クラウド型の納品書受領システムの導入」が最適だといえます。
主なサービスの機能を比較した資料をご用意しておりますので、ご参考ください。
【おすすめ関連資料】受け取り納品書・請求書の電子化ツール比較表
電子化のために納品書受領システムを導入するメリットとは
上記では、納品書を電子化するさまざまな方法について解説し、その中でも特に外部の納品書電子化システムの導入を最適な手段として推奨しました。ここでは、具体的に納品書受領システムを導入することによるメリットを深堀りします。
発行されたその日に受領が可能
従来の紙ベースの納品書は、発行・郵送から到着までにタイムラグが発生してしまいます。
また、届いた納品書は、オフィスに出社して確認しなければなりません。
さらに、届いた納品書に誤りがあった場合は、再発行・再送を待つ必要があります。
電子納品書であれば、発行したその日に受領することができ、もしも記載事項に誤りがあった場合でも速やかに修正版を発行してもらうことができます。
返送の手間とコストの削減
取引先や取引内容によっては、納品書の発行前後に発注書や受領書に問題が発生するケースがあります。
発注書や受領書等の帳票も専用WEBページにアップロードすることができるので、紙の文書を返送してもらう手間やコストを削減することができます。
業務の効率化が図れる
納品書は税法上で7年の保管義務があり、過去の取引で生じた書類を保管し続けていると膨大な量になります。
たとえ適切にファイリングしていたとしても、多くの書類群の中から特定の書類を見つけ出すのには多くの手間と時間がかかってしまいます。
納品書を電子化して保存することで、データベースを検索するだけで参照したい納品書をすぐに見つけ出すことができるようになります。
【関連記事】入金管理を効率よく!納品書・請求書を電子化するメリットなどを解説
紛失の防止になる
紙の納品書は、誤って紛失するリスクが常にあります。
保管する書類の数が増えるほど、ほかの書類に紛れてしまったり、誤って廃棄してしまったりする可能性が高くなるため、注意が必要です。
納品書を紛失すると取引内容の確認が困難になり、支払い処理や経理業務に影響が出るだけでなく、取引先との信用問題にも発展しかねません。
また、税務調査などで必要な書類が見つからない場合は、不備を指摘されるリスクもあります。
しかし、納品書を電子化すれば、データとしてクラウド上やシステム内に安全に保管できるため、紛失リスクを大幅に削減することができます。
劣化を防げる
紙の書類だと、年数が経つにつれ、色褪せたり汚れたりすることで劣化してしまいます。
紙質が古いだけで、触るのも億劫になってしまうでしょう。
紙の納品書を電子化し保管をすれば、そのような劣化の心配がありません。
書類を電子化することで、いつまでも読みやすい状態で保管しておける点もメリットです
【関連記事】経理業務の自動化を解説!自動化の課題とメリット・デメリットとは?
電子化のため納品書受領システムを導入する際の注意点とは
納品書の電子化にあたって納品書受領システムを導入する場合は、導入・運用コストが発生します。
また、紙での納品書の送付を希望する取引先が一定数は存在し、完全な納品書の電子化は難しいケースもあり得ます。
以下に、納品書受領システムを導入する際に注意すべきポイントをご紹介します。
導入・運用コストがかかる
納品書受領システムを導入する際は、基本的に初期費用や月々の運用コストが発生します。
料金形態は主に2種類あり、毎月の利用料金が一定の「定額制プラン」と、枚数に応じて料金が変動する「定額従量制プラン」です。
相場としては月額4万円前後が一般的ですが、システムによっては初期費用が10万円以上かかり、予算確保が課題となる場合があります。
しかし、納品書の電子化により、手作業による確認・入力業務の負担が大幅に軽減されるため、人件費の削減につながる可能性があります。
特に枚数が多い企業では、長期的に見るとコスト削減効果が期待できるでしょう。
【関連記事】毎月の請求書の処理って大変!封筒を開封する手間を省ける方法は?
慣れるまで時間を要する
納品書受領システムを導入すると、業務の効率化が期待できますが、新しいシステムに慣れるまでには一定の時間がかかります。
特に初めて電子化ツールを使用する場合は、データの入力・検索方法、エラー対応などを学ぶ必要があり、導入直後は一時的に業務が滞るかもしれません。
そのため、事前にデモを試し、実務担当者がスムーズに操作できるか確認しておくことをおすすめします。また、マニュアルの作成や社内研修の実施などを行うことで、導入後の混乱を最小限に抑えられます。
いきなり全社的に導入するのではなく、一部の部署や取引先で試験運用を行い、段階的に拡大していくとよいでしょう。
取引先への案内に手間がかかる
新たに納品書の電子化を進める場合、取引先に電子化の旨を案内する必要があります。取引先が数多く存在する企業では、案内をするだけでも一苦労です。
また、納品書の電子化を進めても、紙での納品書の送付を希望する取引先が一定数あることが想定され、完全な電子化を行うことは難しい場合もあります。
指定のフォーマットによる納品書の郵送を求める企業もあることが考えられます。
とはいえ、大半の取引先の納品書を電子化できれば、大幅な業務削減を図ることが可能です。
【関連記事】請求書の電子化における案内状のポイントは? テンプレートも紹介
システム障害により閲覧できない可能性
電子化された納品書はサーバーやクラウド上に保存されますが、システムに障害が発生した場合、一時的に納品書の閲覧ができなくなる危険性があります。
例えば、単価・数量を確認したいのにアクセスできない場合、業務が滞り取引先に迷惑をかけてしまいます。このような事態が続くと、企業の信頼を損ないかねません。
このリスクに対処するためには以下の2つの方法が考えられます。
まず、定期的にバックアップを行いましょう。納品書データを外部システムとオンラインストレージの両方に保存しておけば、システム障害が発生した際にも業務の継続が可能となります。
次に、信頼性の高いシステムを選定することが重要です。納品書の保存システムは数多くありますが、サポート体制が整っており、迅速に障害対応ができるかどうかを確認しましょう。
万が一のトラブルが発生しても納品書の閲覧や処理に支障をきたすことのないよう、事前に対策を講じておきましょう。
納品書受領を電子化するためのシステムの選び方とは
会社に納品書の電子化を行うとなった際に、どのような基準でシステムを選べばいいのか、迷ってしまいがちです。
ここではおすすめの納品書受領システムの選び方について解説します。
電子帳簿保存法の要件を満たしているか
納品書をデータとして保存する際には、電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たしていることが必須です。大きく分けると「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つをクリアしなければいけません。
「真実性の確保」とは、保存されたデータが改ざんされていないことを証明する仕組みを指します。具体的には、以下のいずれかに該当するシステムを選ぶ必要があります。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領できる
- 受領後、遅滞なくタイムスタンプを付与できる
- 訂正・削除を行った際に履歴が残る、または訂正・削除ができない
システムを導入する前に、電帳法に対応しているかを必ず確認しましょう。
電子化の業務負荷をどこまで減らしたいか
納品書受領サービスにおける納品書の電子化の仕組みは、機械による自動電子化と、オペレーターによる人力電子化の2つに分類されます。
前者では、経理担当者がスキャンした納品書画像から、システムが有するAI(人工知能)やOCR(光学文字認識)で自動的に電子化します。
スキャン後間もなく電子化できる点がメリットです。
一方、現在の技術では100%の精度ではないため、電子化完了後に、経理担当者が確認する必要がある点はデメリットといえるでしょう。
後者では、各ベンダー選任のオペレーターが手入力で電子化を行います。
時間は多少かかるものの、高精度の電子化が期待できるため、電子化完了後の確認は不要となります。
スピードと精度の比較で単純に優劣をつけるのではなく、自社の経理担当の業務負荷をどこまで減らしたいかを考え、選定を進めることが重要です。
自社の会計システムに適合できる仕訳データを出力できるか
納品データを会計システムへ取り込む際には、APIを利用する方法と、出力したCSVファイルをインポートする方法があります。
APIを利用するメリットは、経理担当者がデータに直接触ることなく、自動的にシステム間で連携ができる点にあります。
したがって、納品データを月に何度も会計システムに取り込む必要がある場合は、APIによる直接連携が可能なサービスを検討すべきでしょう。
ただし、2021年11月現在、APIリリース実績が各社ともに不十分であるため、CSVファイル経由のデータ連携が主流です。
会計システム毎に、出力するCSVファイルの形式をカスタマイズできる納品書受領サービスも存在するので、検討の際にはCSV負担を大きく捉えずに済むかもしれません。
納品書受領サービスが自社の会計システムに適した仕訳データを出力できるか否かは、必ず確認しましょう。
会計システムとの連携の精度が高いか
納品書受領サービスを導入したものの、自社の会計システムとの連携がスムーズにいかず、無駄な手間が生じてしまったり、場合によってはトラブルになってしまう場合があります。
そのような状況に陥らないために、単に自社の会計システムに連携しているかだけでなく、連携の精度に信頼がおけるかを確認することがとても重要です。
一方で、会計システムとの連携の精度がどれくらい高いかというのは、実際のところ利用してみなければわかりません。
企業によって導入している会計システムは異なるため、サービスの口コミが良いからと言っても、必ずしも自社の会計システムとの連携がスムーズにいくとは限りません。
しかし、連携精度が高いシステムを選ぶための一つの方法として、「経理向けサービスの提供実績がある会社のサービスを選ぶ」というものがあります。
このような会社は、経理業務や会計システムに関するノウハウを十分に有しており、それゆえ提供するサービスは、会計ソフトと高精度で連携する可能性が高いと考えられます。
請求書・見積書等の国税関係書類にも法対応できているか
電子帳簿保存法は、切っても切り離せないものですが、実は電子帳簿保存法の対象範囲は納品書や領収書に限らず、請求書や見積書、検収書等を含んだあらゆる国税関係書類なのです。
そのため、「納品書」だけに対応するサービスを利用してしまうと、例えば請求書や見積書を別の方法で対応せざるを得ないため、完全な効率化は実現しないでしょう。
したがって、すべての国税関係書類を受領・電子化できるサービスを選ぶことが重要です。
コスト負担が最適か
システムの導入には一定のコストが発生するため、導入に伴う初期コストやランニングコストが自社の予算に見合っているか確認しておくことも大切です。
なお、多くのシステムは月額使用料や年間使用料といったランニングコストの形で費用が発生します。十分な費用対効果を見込めるか事前に検討しておきましょう。
【関連記事】受け取る納品書・請求書の電子化サービスの選び方|5つの活用事例もご紹介
コスパ最強!おすすめの納品書受領システムをご紹介
納品書受領システムにはさまざまなものがありますが、その中でコスパを重視するなら「oneplat(ワンプラット)」がおすすめです。
以下に、oneplatの主な特徴をご紹介します。
販売管理・会計システムと連携可能
oneplatは納品データを販売管理システムと連携させることができ、商品名の入力やコードの紐づけ作業を削減可能です。さらに、請求データを会計システムに連携させることで、仕訳等の入力作業も不要となります。
電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応
スキャナを利用する保存方法では、書類を読み取り、検索しやすいように一覧表を作成する手間が発生します。
この作業には時間と労力がかかるだけでなく、適切に運用するためにはルールの徹底が不可欠です。
しかしoneplatで受け取る納品書・請求書は、電帳法およびインボイス制度に対応しています。
面倒な作業をせずに法令に準拠した保存が可能なため、業務の効率化とコンプライアンスの強化を同時に実現することができます。
初期費用0円、月額33,000円と低コスト
納品書や請求書の電子化には、一般的に高額な導入費用がかかりますが、oneplatなら初期費用0円、月額33,000円(税込)で受領する納品書・請求書の電子化が可能です。
さらに、取引先への案内や操作説明の実施、既存システムとの連携を無償でサポートしています。スムーズに移行できるよう支援体制が整っているため、混乱なく電子化を進められるのも大きなメリットです。
oneplatの導入事例
以下では、納品書受領システムoneplatを導入し業務工数やコストを削減した事例をご紹介します。
支払い業務にかかる工数が従来の50%以下に削減(グラフィック・パッケージング・インターナショナル株式会社 様)

紙の製造やパッケージングのソリューションをメイン事業とし、全世界に130ある活動拠点をベースに事業を展開している同社では、経理プロセスや、経理よりも手前のプロセスで各作業をシステム間で連携していませんでした。また、経理での支払い作業では1件ずつインターネットバンキングに手入力するなど、大きな負担になっていました。
oneplat導入後は、会計ソフトからデータをそのまま抽出し、そのデータをoneplat上で自動集計しています。これにより入力作業が自動化され、50%以上の工数削減を実現できました。
▶グラフィック・パッケージング・インターナショナル株式会社様の事例の詳細はこちら
突合作業を月10時間以上軽減(株式会社ケーユーホールディングス 様)

ケーユーホールディングス様は、外注業者から届く納品書がすべて紙だったため、拠点で基幹システムへ手入力する必要がありました。しかし、この作業には手間と時間がかかる上、請求書と突合する際に多くのミスが発覚していました。
例えば、基幹システムへの入力ミスや業者側の請求内容の誤りなど、原因は様々です。そのたびに確認や修正作業が発生し、業務負担が大きいことが課題となっていました。
そこで、納品書と請求書の突合作業を自動化できるシステムを探し、oneplatを採用します。導入後は照合作業が大幅に簡素化され、全体として月に10時間以上を削減することに成功しました。
▶株式会社ケーユーホールディングス様の事例詳細はこちら
150店舗の納品書・請求書管理を効率化(株式会社Ea-quesT 様)

Ea-quesT様は飲食フランチャイズの運営を行っており、150店舗以上の管理を担当しています。
各店舗に届く納品書の管理に加え、売上管理やロイヤリティ計算、請求書の作成など、多岐にわたる業務を行う必要がありました。
こうした課題を解決するため、oneplatを導入。納品書や請求書の管理をデジタル化することで、請求処理の大幅な効率化を実現しました。
さらに、oneplatは利用料金に導入サポートも含まれているため、フランチャイズ店舗の増加にもスムーズに対応できるようになりました。
▶株式会社Ea-quesT様の事例詳細はこちら
月400枚の納品書をペーパーレス化(株式会社セイザンフーズ 様)

株式会社セイザンフーズ様は飲食店を経営しており、店舗が増えるたびに納品書の管理負担が増大していました。
納品書を保管するためのスペース確保に加え、紛失・破損のリスク、重たい書類を運ぶ手間などの課題を抱えていたのです。
この状況を改善するためoneplatを導入し、納品書のペーパーレス化を実現。経理は毎月300〜400枚の納品書を受け取っていましたが、チェック作業がWeb上で完結するようになりました。
Oneplatのその他の事例についてはこちらをご確認ください。
oneplat導入事例の一覧はこちら
納品書の電子化についてのまとめ
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や、新型コロナウイルスの影響によるテレワーク等、企業のデジタル化が求められています。
2022年1月の「電子帳簿保存法」改正により、2024年1月からはデータで受け取った書類(電子取引書類)の出力保存が認められなくなります。
自社で電子化を行うには、サーバーやシステムに関する高い専門性が要求されるため、納品書発行システムの導入をおすすめします。
クラウド型の納品書受領システムであれば、オンラインで作業が完結したり、会計システムとの連携が行える等、多くのメリットがあり、業務効率化にもつながるでしょう。
oneplatでも、本日お話しした「会計システムとの連携」や2022年1月改正電子帳簿保存法とインボイス制度に対応している「納品書・請求書クラウドサービス」を提供しています。
納品書の電子化だけでなく、財務・経理部門の業務コスト削減にも興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。