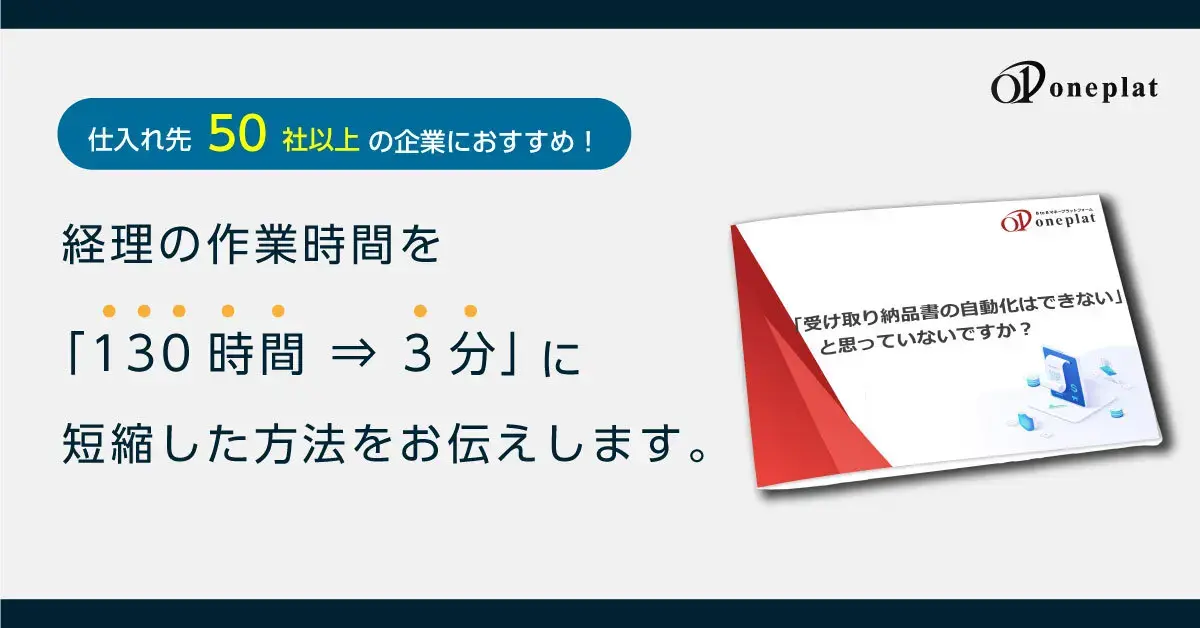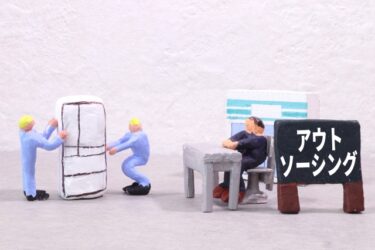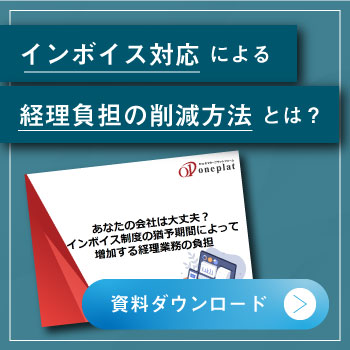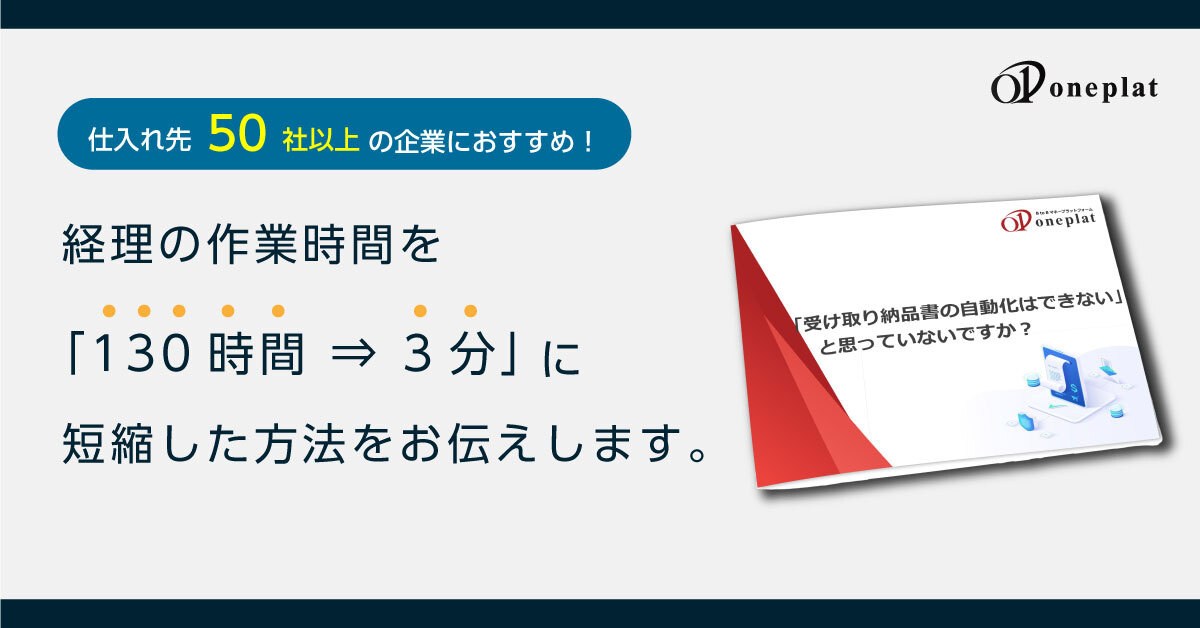中小企業の多くは乗っ取り対策として活用することの多い譲渡制限付株式ですが、実はほかにも効果的に活用できる方法があるのをご存じでしょうか。
今回の記事では、下記について紹介していきます。
- 譲渡制限付株式を導入する目的
- 「発行方法」と「生じるメリット&デメリット」
- 従業員の報酬として活用する方法
それでは順番に見ていきましょう。
譲渡制限付株式とは? わかりやすく解説
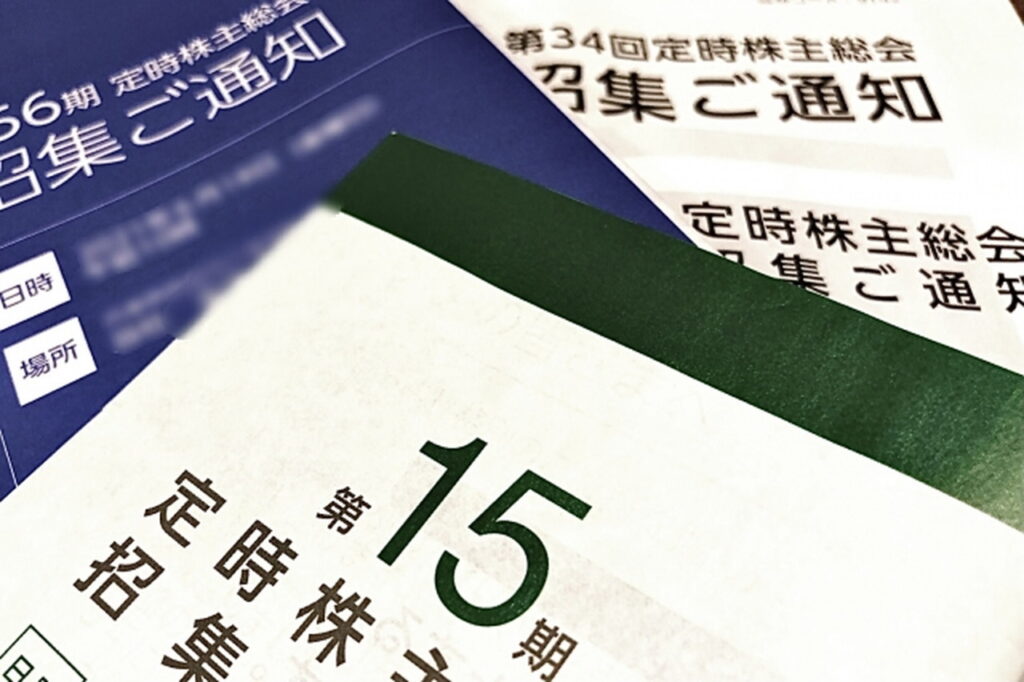
譲渡制限付株式とは「譲渡において制限がある株式」のこと
譲渡制限付株式とは、その名の通り「譲渡について制限がつけられている株式」を意味します。よって、一般的な株式のように自由に売ったり買ったりすることができません。
中小零細企業では、主に乗っ取りを防止することを目的に活用されている場合が多いでしょう。一方、大企業では役員や従業員への報酬として利用するケースが増加しています。
譲渡制限付株式の目的:会社にとって望まない人に株式を保有させないため
企業が譲渡制限付株式を活用するのは、自らの意志によって自社を守るためです。
一般的な株式は誰でも自由に売ったり買ったりすることが可能なので、企業の意思によってそれを止めることはできません。
例えば、過去から現在まで家族経営を行っている企業が、今度も同様に経営していきたい考えを持っていると仮定します。
しかし、その企業が保有する独自のノウハウに目を付けた投資家に、株式を買い占められてしまう可能性は否定できないでしょう。
そのようなケースでも、株式の自由な譲り渡しに制限をかけていれば未然に防ぐことができるのです。
「公開会社」と「非公開会社」の違いは譲渡制限の有無
公開会社とは、会社の法律である定款によって「発行しているすべてまたは一部の株式を自由に譲り渡すことに対して制限をかけていない会社」のことです。ちなみに「公開会社=上場会社」ではありません。上場会社とは、あくまで株式取引所で株式を公開している会社を指しているだけです。
一方、非公開会社とは、定款によって「発行しているすべての株式に対して譲渡することに制限をかけている会社」を指しています。
まとめると、両社の違いは「譲渡制限の有無」ということです。
株式譲渡の自由の原則:「定款の定めによる譲渡制限」は例外
会社法127条で、株主は保有している株式については自由に譲渡できる旨が記載されています。しかも相手が誰かについては定められていないので、全く面識のない人への譲渡も可能です。そしてこの原則に例外を設けたのが、「定款の定めによる譲渡制限」。会社法107条1項1号、そして108条1項4号によって定められています。
特に中小企業では「自分たちの知っている人だけを株主にしたい」というニーズがあるので、譲り渡しに制限を設けている会社が多いのが特徴です。見ず知らずの人による会社の乗っ取りを防ぎたい意向があるのではないでしょうか。
譲渡制限付株式の発行:対象株式の数量による2種類の方法
譲渡制限付株式を発行する方法は、2種類あります。
それぞれどのように行うのか確認していきましょう。
1. 発行する全株式の自由な譲り渡しに制約をかける
「株式を誰かに譲り渡す場合は、会社からの承認を得なければならない規定」を設けることができます。しかしそのためには、定款に決められた事柄を定める必要があります。逆を言えば、定款に定めさえすれば、発行したすべての株式の譲り渡しに制約をかけることが可能になるのです。
設定されているかどうかの確認は、「定款」そして「登記簿謄本」をチェックしましょう。
2. 一部の株式に対して自由な譲り渡しに制約をかける
すべてではなく、一部の株式に対して制約をかけることも可能です。全株式の場合と同様に、定款に記載しなければいけません。
一点、注意点があります。譲り渡しに制約をかける株式の数が一定量を超える場合は、承認できる発行総数を必ず記載しなければいけないことです。
譲渡制限付株式を発行して得られるメリット

譲渡制限付株式の発行によって得られるメリットは、大きく3つあります。
1. 後継者に株式を集めやすくなる
株式の保有数は、そのまま経営に対する発言力の強さに比例します。譲り渡しに制約をかけることで、後継者がスムーズに会社を引き継げるように準備できるでしょう。
2. 会社を乗っ取られるリスクの低減
自分たちの知らないところで、株式を買い集められることを防ぐことができます。
3. 組織の運営コストを抑えることができる
・取締役会を設置する義務がない
ただし、全株式に制約をかけている場合のみです。一部の場合は、設置しなければいけません。
・監査役が不要である
こちらも全株式に制約をかけている場合のみなので注意しましょう。
・株主総会の手続きを簡略化できる
全株式に制約をかけることで、株主総会の開催1週間前の通知でも認められるようになります。また、書面ではなく口頭でも可能になるので、手間がかなり減るでしょう。なお、一部のみの制約の場合は、開催2週間前までに書面によって通知しなければいけません。
譲渡制限付株式の発行で生じ得るデメリット
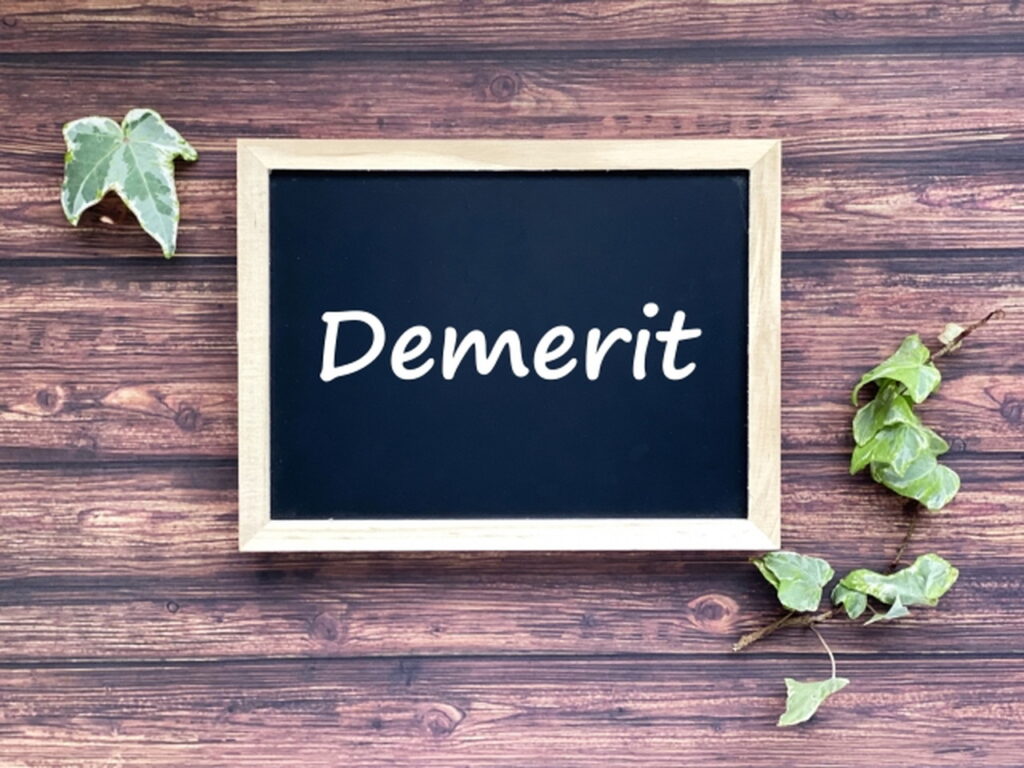
次に、主なデメリットをお伝えしていきます。
1. 会社を乗っ取られる可能性がどうしても残ってしまう
後継者が株式を相続した場合は、ほかの株主から「売渡請求」を行われる可能性があります。しかも、後継者は議決権がないので反対できません。その結果、賛成多数で望まない後継者が誕生してしまい、会社を乗っ取られてしまう可能性は残ってしまいます。
2. 「株式買取請求権」が行使される可能性がある
制約をかけていても、実は第三者に譲り渡すことはできてしまいます。なぜなら、違法ではないからです。さらに、会社に対して「譲り渡すことを認めること」そして「会社による買い取り、または会社が買い取る人を指定して買い取らせること」を主張することができます。こうした可能性をなくすことはできません。
譲渡制限付株式の譲渡であり得る3つのパターン
譲り渡しに制約をかけている株式であっても、すべてを防ぐことはできません。
考えられるパターン3つを紹介します。
1. 株主から会社に譲り渡しが行われる
「買取価格が決まっている」「決まっていない」の2通りがありますが、どちらも企業にとっては平和的なケースです。しかし、もし誰かから買い取る場合は「株主平等の原則」に則って、株主全員に同じく機会を与えなければいけません。
2. 会社が強制的に買い取る
条件を満たしている必要がありますが、企業は「株主からの同意なく」株式を買い取ることができます。
3. 株主が第三者に譲り渡してしまう
本来であれば必要な企業の承認なしに、株主が第三者に譲り渡してしまうことも考えられます。解決方法として「企業がその第三者の株式取得を認める」「認められない場合は、企業が買い取る」という2通りが考えられるでしょう。
譲渡制限付株式を譲渡する手続きの流れ
①会社へ「株式譲渡承認請求」を行う
まず最初に行うべきは、会社に「株式譲渡承認請求」を提出して承認を求めることです。「実際に請求したという事実」を残しておくため、書面によって請求を行うのが良いでしょう。その際は「譲り渡す予定の株式数」「譲り渡し先」等を記載しておくのが一般的です。
②承認機関で譲渡の承認を受ける
会社側は請求を受け取ったら株主総会または取締役会を開き、「普通決議」で承認を認めるかどうかを決定します。なお、普通決議で承認を得るためには次の2つの条件をクリアしなければいけません。
- 議決権総数の過半数の株式を有する株主が出席すること
- 出席した株主の過半数が賛成すること
なお、定款に定めておけば株主総会等を開かずに承認することも可能です。
③承認通知を受ける・譲渡契約を締結する
会社は請求を受けた日から14日間以内に、先方に対して結果報告を行います。もし、何もしないまま14日間が経過した場合は、請求は承認されたものと見なされるので注意が必要です。
会社から承認が出たら、譲り受ける人と「譲渡契約」を締結します。契約を交わす前に、「いくらで譲り渡すか」「支払いはどのように行うか」等について話し合っておくようにしましょう。
④譲渡した株式の名義を変更する
契約が締結したら、「譲り渡す側」と「譲り受ける側」は会社に対して「株式の名義」を変換してもらうように請求しなくてはいけません。
なぜなら、名義の変更が行われないと、譲り受けた人は株主としての権利が認められないからです。
両者ともに押印し資料を作成し、「株主名簿書換請求」を行いましょう。
⑤会社が譲渡制限付株式の譲渡を承認しない場合の選択肢
もし会社が株式の譲り渡しを承認しない場合は、とるべき選択肢としては下記が挙げられるでしょう。
・譲り渡すことを諦める
譲り渡すことなく、現状のまま株式を保有し続けます。
・会社に対して「株式の買い取り」を請求する
会社法140条により、もし請求を受けた場合には買い取らなければいけません。
・会社が指定してきた買取人に買い取ってもらう
会社法140条4項により、会社は買い取る者を指定することができます。
譲渡制限付株式の売買価格はどのように決める?

売買価格を決める方法として、大きく3つ考えられます。
・話し合いによって決定
まずは当事者同士で話し合いを行いましょう。
・裁判所に申請して決めてもらう
もし話し合いによって決まらなかった場合は、裁判所への申し立てを行い価格を決定してもらう方法です。ただし、手続きは複雑で簡単ではないので、専門家のサポートを受けたほうがいいかもしれません。
・会社法で定められた供託価格
話し合いでは決着がつかず、裁判所への申し立ても行わない場合は会社法で定められた価格(1株当たりの純資産額×株式数)で決定されます。
譲渡制限付株式は従業員の報酬として活用できる

譲渡制限付株式を報酬として付与する仕組み
過去には株式を報酬として従業員等に与えることはできませんでしたが、2016年の税制改正によって「現物出資に対して交付する」形であれば可能になりました。
次のステップを踏むことが必要です。
- 債権という形で、従業員や役員に報酬を前払いする
- 従業員や役員から、債権を会社に現物出資してもらう
- 渡してもらった債権との引き換えに株式を与える
ただし「現物出資がない状況で株式を付与すること」「現金出資の引き換えに株式を付与すること」はできないので、注意しましょう。
譲渡制限付株式を報酬に用いるまでの背景と目的
海外では株式報酬を用いることが一般的ですが、日本では固定報酬で支払われることがほとんどでした。日本企業の稼ぐ力を高め、そして人材を育てることで世界と戦える環境づくりが急務だったのです。日本政府は、株式報酬や業績に連動した報酬体系を活用しやすくするために税制改正等を行い、その下地が育ってきています。
また、目的としては下記が挙げられるでしょう。
- 優秀な人材を獲得しやすくなる
- 株主の立場に立った経営を行っていけるようになる
- 役員等への業績向上のインセンティブの付与が、企業の競争力を高める
まとめ
譲渡制限付株式をうまく活用することで企業を守り、さらに従業員のモチベーション向上や企業力UPにも繋げることができるかもしれません。
メリット&デメリットを理解した上で、もし「譲渡書人請求」等が行われても慌てずに対応していけるように知識を入れておきましょう。