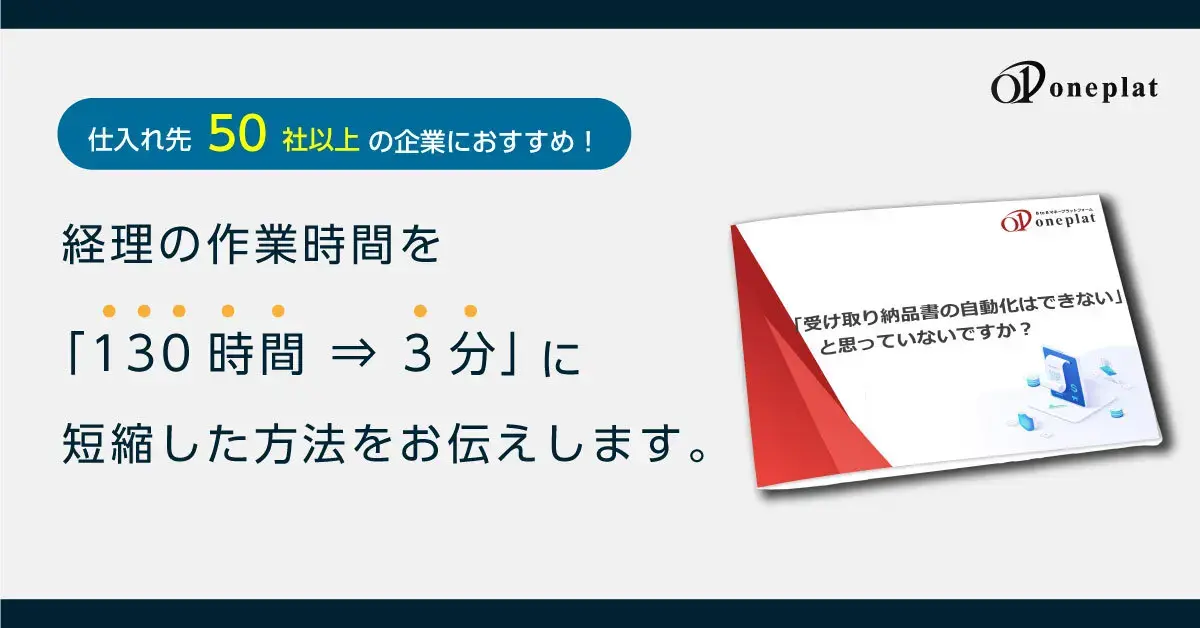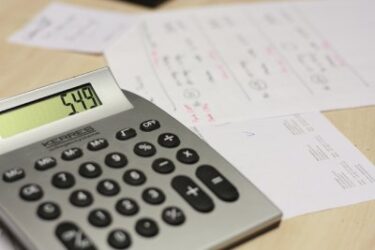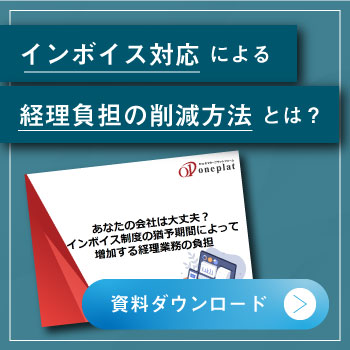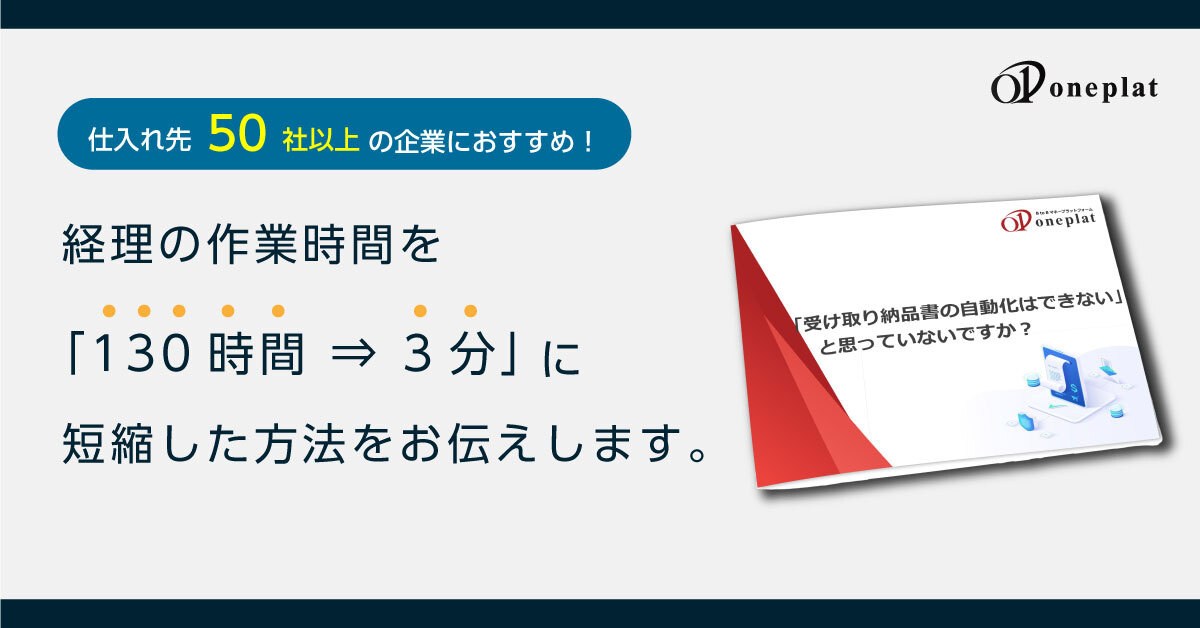ビジネスの現場で目にする機会が多い書類ですが、具体的にどのような情報を記載しておくべきかわからない方も多いのではないでしょうか。必要事項に不足があれば企業間のトラブルを招いてしまう恐れもあります。本記事では、発注書・納品書・請求書の役割から取引の流れ、必要な記載事項、注意点まで徹底解説していきます。
発注書、納品書、請求書。それぞれの書類の意味とは?

ビジネスの場において、これらの書類はどのような目的で利用されているのでしょうか。ここでは、各書類の意味や目的について見ていきましょう。
発注書
取引相手が提出した見積書に対して、発注者が発注の申し込みを意思表示するために提出する書類です。法的に義務付けられているわけではありません。しかし、認識の違いによるトラブルを避けて、取引を円滑に進めるために提出されることが多いようです。
書面には、商品やサービスの詳細や期限、提出方法等を記載して明確にしておくことが大切です。注文書と呼ばれることもあります。
納品書
商品やサービスの内容、納品日を確認するための書類です。発注を受けた商品やサービスを取引相手に納品する際に発行して同封します。納品が完了したという意味合いも持っています。
こちらも法的に義務付けられているわけではありません。しかし、取引相手は納品書と納品物が一致しているか確認でき、取引がスムーズになることを考えると、発行しておいた方が良いでしょう。また、安心感を与え、信用を得ることも期待できます。
請求書
検収書が提出されたら、正式に代金の支払いを請求するために発行する書類です。支払いの請求忘れや、未払い、金額に関する認識の違い等の発生を防ぐ目的があります。
取引相手はこの請求書の内容に沿って代金を支払うため、請求先の会社名、振込先等の必要事項を漏れなく記載しましょう。また、正式な発行であることを証明するために角印で捺印します。
企業間での取引の流れと必要な書類(発注書、納品書、請求書等)

受発注において、先に述べた書類以外にも企業間では様々な書類がやり取りされています。ここでは、取引の流れとやりとりされる各書類について見ていきましょう。
見積書を発行して商品の価格を把握する
買い手企業は、契約前に商品やサービスの価値が適切であるか検討する必要があります。これは日常生活において、コンビニやスーパーでモノを買う時のように単純ではありません。注文を検討している商品やサービスの詳細や数量を売り手企業に伝え、金額がいくらになるか提示してもらうことが必要です。
そのため、買い手企業は売り手企業に見積書の発行を依頼します。買い手企業はより優れた商品やサービスを低価格で発注したいと考えますので、複数の売り手企業から見積書をもらい比較・検討することもあります。複数の見積書を比較することで、より良い条件で発注が可能となるでしょう。
注文書を発行して商品の購入を伝える
買い手企業は提出された見積書を確認して、内容や金額に問題がなければ売り手企業へ申し込みを意思表示するために注文書(発注書)を発行します。注文書には品目や数量、金額、希望納期等を記載しておきましょう。
書類として注文内容を残しておくことで、その後に起こり得る認識の食い違いといったトラブルを防ぐことが期待できます。先ほど法的に義務付けられているわけではないと述べましたが、下請法が適用される企業は発注書を交付することが必須ですので注意しましょう。
下請法は親事業者と下請事業者の関係を対等にするために設けられています。発注側である親事業者が注文書を発行しないと、不正を行い下請事業者が不当な扱いを受けてしまう可能性があります。それを防ぐために、証拠となる注文書の発行が義務付けられているのです。
納品書を発行して商品の提供を知らせる
注文書を受けとった売り手企業は、商品やサービスを記載されている内容通りに納品する必要があります。この時に売り手企業側で発行するのが納品書です。これを納品物に同封して納品することで提供が完了したことを買い手企業に知らせる目的があります。
また、発注した商品やサービスが見積書通りに納品されているか買い手企業側も確認できます。複数の納品物がある場合は、どの商品やサービスが納品されたかわからなくなってしまうこともあるでしょう。こうした混乱やトラブルを避けるためにも欠かせません。
納品書の記載内容は基本的に見積書と同様になります。合意なく変更がされていれば契約違反になってしまいます。そのため、発行時には見積書と納品書の内容に相違がないかしっかり確認しましょう。
検収書で商品の受け取りを通達する
納品物と納品書を受け取った買い手企業は、発注内容と実際の納品物が異なっていないか確認する必要があります。例えば、商品の種類や数量、内容に加えて、傷や汚れ、初期不良がないか等を検品します。問題がなければ受け取りが完了したことを売り手企業に伝えましょう。この時に発行されるのが検収書です。
契約通り納品物に問題がなかったことを証明するために必要です。また、たとえ検収書を提出した後に不良品や不具合が発見されてもクレームや契約解除はできません。しっかり検品を行って問題ないことを確認してから発行しましょう。このように企業間のトラブルを防ぐためにも大切な役割を果たしています。
請求書で商品の代金を請求する
検収書を受け取った売り手企業は、正式に代金の支払いを請求するために請求書を発行します。送付漏れがあったとき、企業によっては請求書の送付を催促してくれるが、基本的に請求書を提出しないと支払いをしてもらえないことが多いようですので、請求書の送付漏れには注意しましょう。
未払いや支払いの遅延等のトラブルを避けるためにも、わかりやすい内容かつ必要な内容を忘れずに記載して作成します。
発注書、納品書、請求書の必要記載事項と注意点

認識の食い違いやトラブルを避けるためにも、各書類には必要事項を忘れずに記載する必要があります。ここでは発注書、納品書、請求書作成の際の必要記載事項と、作成時の注意点について解説していきます。
発注書の必須記載事項と注意点
買い手企業が発行する書類となります。
必須の記載事項は以下の通りです。
・発行年月日
・宛先
・対象の商品やサービス名と数量
・単価と合計金額
・納品希望日
・納品場所
・発行者側の企業名と住所、電話番号、社印
・有効期限
特に漏れに注意してほしいのが「有効期限」です。記載しておかないと、古い見積書で発注を依頼されることがあります。発行当時から現在までの間に、仕入原価等の企業の状況が変わっていることもあるでしょう。古い見積書の記載通りだと赤字になってしまうこともあり得ます。
しかし、トラブルを避けるために受けざるを得ないということにもなりかねません。そういった状況を未然に防ぐためにも有効期限の記載が必要です。
納品書の必須記載事項と注意点
売り手企業が発行する書類となります。
必須の記載事項は以下の通りです。
・発行年月日
・宛先
・納品した商品やサービス名と数量
・単価と合計金額
・発行者側の企業名と住所、電話番号
発行は義務ではありませんが、納品したという証明になるため一般的に発行されることが多いようです。買い手企業側も、発注した内容と実際納品された商品やサービスが異なっていないかチェックできて、経理処理に役立つこともあります。
請求書の必須記載事項と注意点
売り手企業が発行する書類となります。
必須の記載事項は以下の通りです。
・発行年月日
・宛先
・納品した商品やサービス名と数量
・単価と合計金額
・発行者側の企業名と住所、電話番号
・支払いの振込先情報
・支払期日
基本的に、買い手企業は請求書を受け取ってから支払いを行います。請求書を提出していないと支払いが行われないこともあるので、取引完了後すみやかに発行しましょう。
まとめ:各書類(発注書、納品書、請求書等)の意味や必要なタイミングを理解すれば業務が効率的に行える!

本記事では、各書類の役割から取引の流れ、必要な記載事項、注意点等を解説しました。企業同士がスムーズに取引するためにも欠かせない書類であることがおわかりいただけたかと思います。ただ発行するのではなく、必要な項目をしっかり把握して、トラブルを未然に防げるように作成を行いましょう。