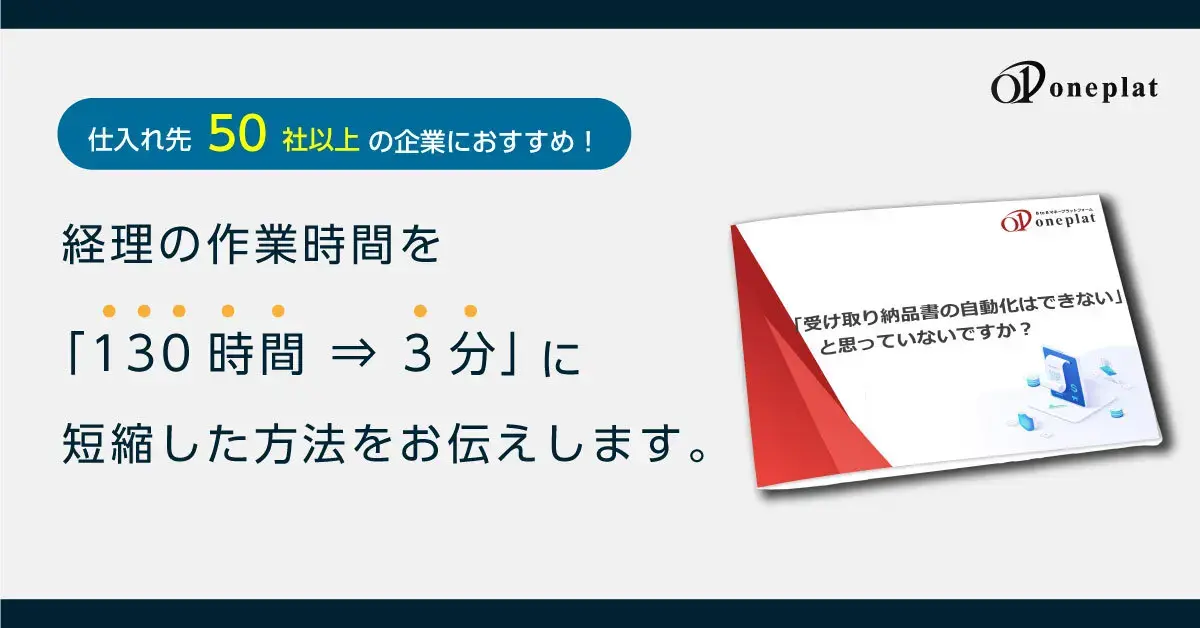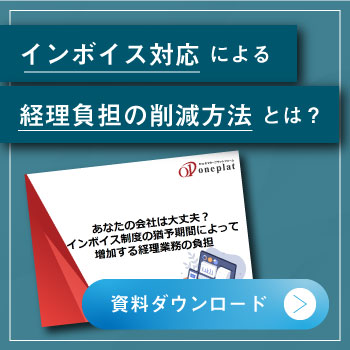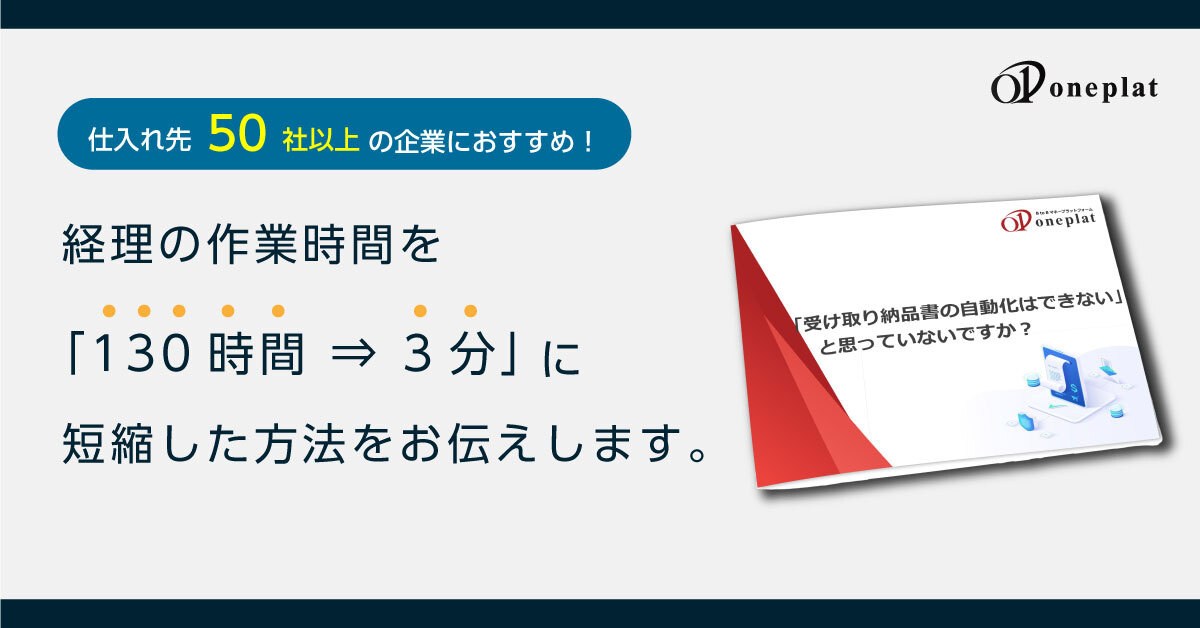DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にあたって、重要な要素のひとつとして位置付けられるのが「データの活用」です。実際、DXの定義として経済産業省は、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する(略)」とガイドラインに記しています。DXとデータはまさに両輪とも言える関係性にあり、DX推進のベースとして、統計学およびデータを活用していく環境は不可欠なのです。今回、統計学のエキスパートとして幅広く活躍する西内啓氏に登場いただき、データ活用とDXが企業にもたらす変革について話を聞きました。
DXを推進する上で必要な3つのポイント
DXについてまず言えるのは、多くの日本の企業にとって、本当の意味でまだ手がつけられていないということ。大企業・中小企業ともに、DXがうまく進んでいるところはほとんどないという印象です。
その理由として、DXという言葉が流行する一方、定義が曖昧なために正しい理解が進まない点が挙げられますが、それを払拭する意味でも経済産業省はいま、DXを推進する上でのポイントとして3つの事柄を挙げています。
ひとつは、変革するのは単一のものではなく、製品や企業の組織、業務のオペレーション等、様々なものであること。2つめが、データとデジタル技術の両方を活用すること。そして3つめは、他社との競争優位性を作ることが重要である点です。こうした3つの要素を推進することができて初めてDXであると位置づけています。

DXでツールのカスタマイズを優先することの落とし穴
企業活動を持続していくには、様々なものを変革することが必要であるにも関わらず、これまでの日本の企業は伝統的に、業務ツールのほうをカスタマイズしてきたように思います。つまり、ツールを変えていくことを優先して、業務の中身を変革しようとしない。DX本来の意味である、トランスフォーメーションを行わない形で企業のIT投資が進んできたように思うのです。
これはやり方としては大きな間違いで、今や様々なソフトウェア等、業務ツールは非常に便利になっているわけですから、業務のフロー自体を変えてツールはそのまま活用したほうが、コストだって低く済みます。
エンジニアが何カ月も稼働してシステムをカスタマイズするよりも、実務のオペレーションを変えてしまって慣れていくほうが効率的であり、社員の負荷も軽いものになる。こうした柔軟性の無さによってトランスフォーメーションが進まないことが、DXが十分に進まない原因のひとつと言えるのです。
DXの前に、課題のボトルネックを明確にする
ではDXにおいて、データとデジタル技術の両方を活用するとはどういうことか。
データの活用を考える前に必要なのが、自社にとっての課題を明確にすることです。直面する課題を明らかにすることなく、データありきで考えてしまうとなかなか前には進みません。このまま売上を伸ばしていける余地があるのか、売上増は見込めないので、コストを抑えることで成果を出していくのか。いずれも難しいため、新規事業を作らなければならないのか――。こうした課題設定を明確にすることが必要です。
次に、課題のボトルネックになっている部分を把握することも大事です。アプローチできる見込み客の先が少ないのか。逆にアプローチ先のリストは多くあるのもの、具体的な営業施策が不十分なのか。アプローチは行っているけれど、成果につながらないのか…。
どこに問題があるかを議論し、それに紐づくデータを集めていくことが、最初のステップになることをまずは理解してほしいと思います。
ゴールに直結するデータ「アウトカム」から優先的に収集する
では具体的に、どのようなデータを集めていけばよいのでしょうか。基本的には、課題解決というゴールを認識し、それに直結するデータ(アウトカム)であると言えます。
つまりは、集積が可能なデータの中で、ゴールに直結するものは何か? を考えるのが大事なポイントになるわけです。
例えば、それが売上を伸ばすための情報としましょう。企業のなかで、売上に関する情報はExcelや社内の業務システム等に膨大な量があるはずで、その中のゴールに直結していくデータを把握します。自社の売上が仮に10億だとしたら、それをどう分解していくかが大事なステップになるのです。
その売上は、顧客が買ってくれた積み上げという見方もあれば、営業担当が売った積み上げとしての見方もできます。中には、良い顧客もそうでない顧客も含まれていますし、多く売っている担当者もそうでない人もいる。また、売れている商品と売れていない商品もあるでしょう。1商品ずつが積み上がった10億円の中身をデータとして把握し、各々の違いを把握していくわけです。
例えば、これだけ案件数があるのに、全然注文が取れていない…ということが仮に課題であるなら、取れている案件と取れていない案件の違いを明確化します。
中小企業は一定スパンの中でそうした違いが必ずあります。成功しているものに共通する何かを考えた時、取るべきアクションは2つしかありません。成功する条件に当てはまっていないものを、条件に当てはまるように何かを変えることができるか否か?がひとつです。
2つめは、変えるのではなく「狙う」という手段になりますが、成功しやすい案件が当初から得られるよう、Webマーケティング等の別の手法を活用することを考えます。
データを活用して必要なものを見定めていくことをやっていけば、ヒットを得るための商品やサービスの訴求力もおのずと高まると思います。

「何がどうなればうれしいか?」をDXと結びつける
また、別の観点からは、支援先等で「よく出ている議題だけれど、解決しない問題はありますか?」とちょっと意地悪な質問をすることもあります。多くの企業の場合、「なんとかしなきゃ」「頑張ります」で終わっていることが多い。ただなんとなく頑張ります、では限界があるのは当然で、だからこそ課題解決や改善策にDXをどう絡めていくかは大事なのです。
ゴールとして最大化したい、または最小化したいものを明確化することから始まり、どのような中身の集積によってその数字になっているのかを分解していきます。それによって、自社がアクションを起こしていくターゲットを導き出すわけです。
課題となるのは、商品やサービスの中身かもしれないし、顧客の属性、または人材の面にボトルネックがあるのかも知れません。データの集積と分析によって、トランスフォーメーションを起こす目的を明確にしていく。これがデータをDXに結びつけていく基本的な考え方であり、競争優位性のベースになるものです。
なかには、課題設定を間違ってしまうところで既につまずいてしまう経営者の方も見受けられます。それは何も難しく考える必要はなく、例えば「何がどうなればうれしいか?」を自問自答してみるだけでいいのです。
経営のトップたる者、「今よりもこうなればうれしい」というものは必ずあるはず。シンプルな視点で考えてみることが、DXにおいて不可欠なトランスフォーメーションのもとになっていくと思います。
NEXT ▶︎ #2 データを「正しく」活用し、DXを推進せよ
■ 西内啓(にしうち・ひろむ)
統計学者/ 株式会社データビークル取締役副社長 最高製品責任者
1981年兵庫県神戸市出身。東京大学医学部卒業後、東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野助教、大学病院医療情報ネットワーク研究センター副センター長、ダナファーバー/ハーバードがん研究センター客員研究員を経て、2014年株式会社データビークルを創業。データに基いて社会にイノベーションを起こすための様々なプロジェクトにおいて調査、分析、システム開発および戦略立案をコンサルティングする。また日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)アドバイザーも務める。著書『統計学が最強の学問である』(ダイヤモンド社)はシリーズ累計約50万部を突破するベストセラー。講演では、統計学がビジネスの意思決定にもたらす影響力や、統計学がこれまで生み出してきたインテリジェンス、ビジネスパーソンに必要とされるデータ分析能力について実践例を交えて伝えている。